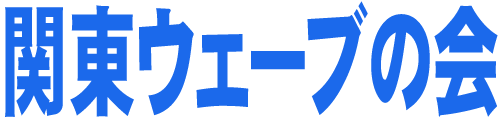�V��
�V��
22�N�Ԉ��ݑ��������{�g���[���̒f��ɐ������܂����B
�x���]�W�A�[�s���ŋ��̃��{�g���[����1�N6���������Č���f�A�f���6�������o�߂��܂����B
��������]���ƁA�ŏ���12�N�Ԃ�0.5mg�̃��{�g���[����1������40�����炢�B�c��10�N�Ԃ�1����20�����炢�ł��B
���L����̐���ł��B
����́A���{�g���[��0.5mg1���̓f�p�X0.5mg��6���ɕC�G����͉�������ƒm���āA�ł��邾�����܂Ȃ��悤�ɂ�������ł��B
�x���]�W�A�[�s���̒f�����]�������̓A�V���g���}�j���A���Ƃ����x���]�W�A�[�s���̒f��ɂ��Ă̐�����������܂��B
���ɂ��x���]�W�A�[�s���f��Ɋւ���YouTube�����Ameba�u���O���Q�l�ɂȂ�܂��B
�������{�g���[���̒f��ɐ��������v���̓x���]�W�A�[�s���̒f��ɐ���������l�B�̒m�������������ł��B
������Ԓ��͔����Ǐ�A���E�Ǐ�A�}���Ǐ�ő����ꂵ�������ł��B
���̓��{�g���[�����~�߂Ė{���ɗǂ������Ǝ������Ă��܂��B
�����ݎ���6�����ȏ�����_���S������łȂ��ł��B
�ȉ��͐��_�Ȉオ�����_��ɂĂ̘b�ł��B
�R�����g��ǂ�ł��������ƁA���̐��_�Ȉ�̈ӌ��Ɏ^������l�Ɣ�����l�����X���炢�ł��B
�����̂�����͎����̃��e���V�[�Ŕ��f���Ă��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@��
https://www.youtube.com/watch?v=BO5bIw6zyyA&t=253s
 �V��
�V��  2023/10/31(Tue) 17:00 No.28451
2023/10/31(Tue) 17:00 No.28451
�R�J�C���A�o���܂Ȃǂ̓h�[�p�~���Ď�荞�ݑj�Q��Ńh�[�p�~���������܂��B
�x���]�W�A�[�s����210�N�̃C�M���X�̃l�C�`���[�Ƃ����G���ŁA������W�삩�瑤���j�ɂ����ăh�[�p�~����������ƕ���Ă��܂��B
�ϐ����o���Ă��Ȃ��]�ɍ��e�ʂ̃x���]�W�A�[�s������N��Ԃ̂悤�Ȋ�ٔ������N�����܂��B
���͂���ŁA�����ӂ�3�{�g���[���������Ȃ���ނ悤�ɂȂ����N��ԂɂȂ����Ɣ[�����܂����B
�܂��A���a�ɂ͔]�̉��ǂŋN���邤�a�ƃh�[�p�~���̕s���ŋN���邤�a������ƕ�����܂����B
�]�̉��ǂŋN���邤�a�͎��ӎv�l�ɂȂ�A�h�[�p�~���s���ŋN���邤�a�͑��ӎv�l�ɂȂ�܂��B
�x���]�W�A�[�s���Ȃǂ̍�p�@���Ȃǂ��\���������悤�Ǝv������AGoogle�����Ȃǂ��đ����ȕ�������K�v������܂��B
 �����邩
�����邩
�͂��߂܂��āB
�o�ɐ���Q�U�^�ŁA��Q�Ҙg�œ����Ă��܂��B
���̉�Ђɓ]�E����2�N��B���܂ł͉��Ƃ��R���g���[���ł��Ă����̂ł����A�y�N�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�t�����Ƃ��o�����A�������ܔ����̐^���Œ��ł��B
�������o���̗\��ł������A���s�����i�ɓ����A�A�����邱�ƂɂȂ�A�����U��Ă��鎩�������ɂȂ�܂��B
�܂��A��Q�Ҙg�Ƃ����Ă�������Q�҂ƒm���Ă���̂͂��������ł���A��������Ȃ����͂�U��Ȃ��悤�Ɉ���������Ă��܂��ǓƂɋ߂���Ԃł��B
����ȏ�ԂłȂ�Ƃ������Ă��܂����A�����悤�ɂȂ�Ƃ��ς��Ȃ��瓭���Ă�����͂�������Ⴂ�܂��ł��傤���H
�����A����������Ȃ�ǂ�ȕ��ɋƖ���l�ԊW���\�z�A�t�������Ă���̂��������肢�����ł��B
�X�������肢���܂��B
 tori
tori  2023/12/08(Fri) 14:49 No.28466
2023/12/08(Fri) 14:49 No.28466
2�����O�̓��e�Ȃ̂œǂ�ł��������邩�킩��܂��A
�C�ɂȂ����̂ŕԐM���܂��B
���͈�ʘg�ł̋Ζ��ł����A�ꕔ�̐l�͏�Q�Ҏ蒠�������Ă��邱�Ƃ�m���Ă���̂ŁA���������邩����Ɠ����Ȃ̂��ȂƎv���܂��B
�d���́A�Ƃ肠�����o���邱�ƂɑS�͂ł��B���ꂪ�ł��鎞�_�ł܂��Ǐ�͌y���̂��Ǝv���܂����A����ł��x�E������A���ނ����肵�����Ƃ�����܂��B�����A���Ȍ����ň��z�Ɋׂ�̂����킢�̂ŁA�Ȃ�ׂ��撣���ďo���Ă܂��B
�܂��A�����������Ȑ��i�������̂ł����A���l�Ɣ�r���Ċ撣���ĔR���s������A���������邱�Ƃ���Ђɍv���ł�����@�Ȃ̂��Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B���̉�ЂƎ����Ƃ̊W�ɂ����Ǝv���܂����A��i�ɂ͎����̈ӌ���`���܂����B
�o�͂��Ă��܂����A�������܂�̒��͗ǂ��Ȃ��A���z�̎����Ɛ^�t�̐U�镑�������Ă��܂��A�������Ȍ����ł���ǂ��ł��B
�d�����ق�2�l�̐��ŁA�x�e��1�l�����ԂɎ��̂ŁA�R�~���j�P�[�V�������������ޕK�v���Ȃ��̂Ŋy�Ȃ̂�������܂���B���Ƃ����Ē��������킯�ł��Ȃ��Ǝv���܂��i���ۂ̂Ƃ���͒N�ɉ����v���Ă��邩�킩��܂��j
����ł��v���C�x�[�g�ł́A���̗ǂ�������y�Ƃ̖����A�����ł��Ă����Ȃ���h�^�L�������Ă��܂��܂����B�{���Ɉ������Ƃ������Ǝv���܂����A���Ƃ����čs����ł��Ȃ��ǂ����悤������܂���ł����B
�̒��ɂ��Ă͗\���s�\�Ȃ̂ŁA���l�ɖ��f�������Ȃ��悤�ɗ͈�l�ʼn߂�����������܂��A�F�B�����܂���B����ȓ��X�ɈӖ������o�����������Ƃ����̂��{���ł��B
 yuko
yuko
�X���ɓ�����2�T�Ԏ��������킸�A3�T�Ԗڂɂ����Ɣ����܂����B���͂��̉e�����T�X���Ă��܂��B
�������������܂őމ@���Ȃ��o��œ��@�����̂ł����A��̃g���C�E�A���h�E�G���[�͑̂��C�������c�����ł��ˁB
���a�҂���̃u���O���y���݂ɓǂ�ł���̂ł����A�R�����g���悤�Ǝv���Ă��t�F�C�X�u�b�N�̃p�X���[�h��Y�ꂽ�̂Ń��O�C���ł����c�@
�F����A���̕a�C�Ɛ�����̂͑�ς����ǁA�撣��܂��傤�ˁB
 �ς��
�ς��  2023/09/23(Sat) 18:03 No.28443
2023/09/23(Sat) 18:03 No.28443
�Ȃ��牞�����Ă܂���(*^-^*)
����������Ȃ��ł��������ˁB���͋x�{�̎������ȁH
�킽�������@���Ă܂����B�F����@yuko����̖����ł���
�ς��
 yuko
yuko  2023/09/23(Sat) 19:29 No.28444
2023/09/23(Sat) 19:29 No.28444
�����Ȃ��`
�����W�^�o�^�����ɋx�{���܂��B
�ł��A����ς�ł��Ă��܂��܂��ˁc�c
 �܂�
�܂�
�͂��߂܂���
��A�Q�t����������X�������Ă��܂����ƂɔY�܂���Ă��܂��B
�ȑO�͍�����Ԃœ����O���O������ĐQ��Ȃ������̂ł����A�ŋ߂͋C��킹�邽�߂Ƀl�b�g�ŃE�B���h�E�V���b�s���O�����Ă��܂��B
�����O�͔����ƂȂ��ق��Ƃ���̂ŁA�����Ă��܂������A�������ɏK��������Ƃ܂����̂ʼn䖝���Ă��܂��B
������N���Ă���̂�����ǂ��Ă���Ɗ����ɓ�����邪�ɂ����ĐQ�����Ȃ��Ƃ����̂����邩������܂���B
��ӂ������Ԃ����Q��Ă��Ȃ��āA�����ɉe�����Ă��܂������œ�x�Q���������̂ł����A�ł��邩�ǂ����E�E�E
�����悤�ȑ̌��̕��͂���������ł��傤���B
��낵�����肢���܂��B
 yuko
yuko  2023/08/30(Wed) 13:44 No.28439
2023/08/30(Wed) 13:44 No.28439
�������������܂������Ȃ��āA���͓��@���Ȃ̂Ŗ�ӂ��������Q�����Ă��܂��A�Q�t���Ȃ��A�g�C���ɋN�������Ɩ���Ȃ��A���邭�Ȃ�Ɩڂ��o�߂Ă��܂�(�a���͎Ռ��J�[�e�����Ȃ���ł�)���Ԃ͖���Ȃ����A�ق�ƂɎ苭���ł��B
�厡��͖��܂̎�ނ�ς�����A���ރ^�C�~���O��ʂ�ς�����A�F�X����Ă݂߂܂����A�܂��܂�������������A����Ȃ��ē���������ǂ���������܂��B
�悭������u�K�������������v�u���͂����ƋN����v�u3�x3�x�o�����X�ǂ��H����ۂ�v�����H���Ă��A�Ȃ��Ȃ����E�ʋ��ɏ[���Ȑ������Ƃ�܂���B(�K�x�ȉ^���͟T�Ȃ̂Ŗ����c)
����ǂ��ł��B
�܂₳�������ǂ��ł��傤�ˁB
���ʂɁA��͖����āA���͖ڊo�߂āA���͊����������ł��B
 �ڂ���
�ڂ���
���͂悤�������܂��B
��ӓ��e���܂����L�����A�폜���Ă��������������e���܂����B
����폜�p�X���[�h���L������悤�ɂ��܂��B
���萔�����܂����A��낵�����肢���܂��B
�L���ԍ���28431����̈�A�̋L���ł��B
���݂܂���ł����B
 ������
������  2023/08/30(Wed) 07:17 No.28435
2023/08/30(Wed) 07:17 No.28435
���w��̃X���b�h���폜�����Ē����܂����B
������ł����A�������ł��܂��̂ʼn����Ȃ�����������ĉ������B
������̃X���b�h(No.28434����)�����Ԏ������܂�����A�폜�v�v���܂��傤���A�A�A�H
��낵�����肢���܂��B
������
 �˂�
�˂�
���r�o�������Ă��܂����̂āA����Ȏ��ԂɎ��炵�܂��B
yuko����A�����ǂ̊F����A�ɕs�K�ȏ������݂����Ă��܂��A�����f�����|�����܂����B
�폜�p�X���[�h�͓���Ă����̂ŁA�������݂��폜�v���܂����B
�F����ɏ����ł��A�S�̕������K���l�A�F���Ă��܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
 ������
������  2023/08/27(Sun) 04:21 No.28425
2023/08/27(Sun) 04:21 No.28425
�S�R�s�K�ł͂Ȃ��ł���A�A�A�I
�܂����C�y�ɏ������݂���ĉ������ˁB
����Ƃ���낵�����肢���܂��B
������
 yuko
yuko  2023/08/27(Sun) 11:02 No.28426
2023/08/27(Sun) 11:02 No.28426
�ł��A�ŏ��ɏ������ނƁA���X�͋C�ɂȂ�܂���ˁB
�������̕Ԏ����˂˂����S�z�����Ă��܂����̂Ȃ�A�\����Ȃ��ł��B
 �˂�
�˂�  2023/08/27(Sun) 15:20 No.28427
2023/08/27(Sun) 15:20 No.28427
�����Ayuko����̂��Ԏ��ŐS�z�ɂȂ�����ł͂���܂���̂ŁA�ǂ������C�ɂȂ��炸�ɁB
����ǂ��Č��t�������Ȃ��̂ŁA�Z���Ŏ��炵�܂��B
 ������
������
�˂˂����
����Đe�L���ɂ��ꂽ�L���́A���L�X���b�h�̃��X�Ƃ��Ĉړ������Ē����܂����B
�܂��A�L���̍폜�A�C���̎d���ł����A���e��ʂɁu�C���E�폜�p�p�X���[�h�v�Ƃ����̂�����̂ŁA���ɓ��e���鎞�͂�������L�����Ē����āA�f���̈�ԉ��ɃX�N���[�����Ē����ƋL��No.(�Ⴆ���̋L����No.��28423)�ƃp�X���[�h���L�����闓������̂ŁA�����炩�炨�肢���܂��B
����ꍇ�͂�����ł��ړ���폜�͂ł��܂��̂ŁA�����Ȃ����\���o�������ˁB
����������낵�����肢���܂��B
������
 yuko
yuko
����ɂ��́B
�N�T��10�N�A���������Ă͐Q���ސ������J��Ԃ��Ă�2�^�̎�w�ł��B����10�N�͒�l�����Ԃ��L�[�v���āA�����Ȑ��������Ă��܂����B
�Ƃ��낪�A�O�̓~����C���������������Ȃ��ċꂵ���Ȃ鎖�����܂ɂ���A�N�����͉Ƒ��C�x���g����������A���X�������������N�T�̏Ǐ͂�����o�Ă��܂��܂����B
�ډ��͍�����ԂŁA����A�H�ׂ�A���������čl����A�̂����A�l�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����A�قډ����ł��Ȃ���ł��B���݂͂قڐQ������ł��B
�O��T�ɂȂ������������̂������Ȃ��āA�Ђ�����Ƃł����Ƌx��ł���ł����A����͉����ł��Ȃ��̂ɓ��̒��͎����̎���i�߂�悤�ȍl�����N���Ă���̂ŁA���Ԋo�����Ă��āu�ӎ����݂鎖�v���̂��Ђǂ��c�������Ԃ�����܂��B
���a�҂݂̂Ȃ��܂́A���̐g�̒u�������Ȃ������Ƃǂ��܂荇���Ă����܂����H�@���͗N���Ă���C�����̃c����(�s����ł�)�ɂǂ��Ώ����ėǂ����킩��܂���B�ǂ����A�A�h�o�C�X���肢���܂�(�G߄D�)
�m���Ă���肾��������(�������)�Ȃ��Ă݂�ƌ��t�ɂł��Ȃ��ꂵ���A���������Ȃ��A�s���⋰�|�ɒׂ��ꂻ���ł��B���̏��ς��܂ł̋C�����̎����悤�������Ă�������K���ł��B
 �ڂ���
�ڂ���  2023/07/21(Fri) 22:40 No.28395
2023/07/21(Fri) 22:40 No.28395
�܂��A�ԐM���x���Ȃ�܂������Ƃ����l�т��܂��B�ڂ����ł��B
yuko���A���ƂĂ����炢�ɂ��邱�Ƃɒu����Ă��邱�ƁB����������Ԃ͂��т��ьo�����������Ƃł��̂ŁA���̕s����ł�̋C�����B
�܂��A�C���͟T�Ȃ̂ɍs���I�ɏo�Ă��܂����Ƃ��Ă��܂��|����(�����̏ꍇ�����ł���)�A�ɂ��قǕ�����܂��B
yuko����̓��e��q�ǂ���ƁA������e���傫��2����܂���ˁB
�@�s���E�ł�̑Ώ��̃A�h�o�C�X
�A������Ԃ������܂�܂ł̋C�����̂����悤
���̂������ɂȂ��Ă��邩�́A�킩��Ȃ��̂ł����A�����̂Ƃ���A�x�����Ă��錾�t������܂��B
������̃u���O�ŁA�ڂɂ������t�ł����A
�w�o����Ƃ��ɏo���邱�Ƃ��o���邾���x
�Ƃ����V���v���Ȍ��t�ł��B
���͍�����Ԃ̎��Ɏd�������Ƃ��C�͂��ӂ�i���čs���Ă��A�X�ߎ��ŐQ�Ă��܂����肵�Ă��܂����B������J��Ԃ��Ă��܂����B
�������A��i�ɂ͓]�����Ă���Ƌl�ߊ��܂����B�܂��A�Ă���悤�ȕs����ł肪�P���Ă��āA�ʂ��Ă����N���j�b�N�ɓd�b���āu���̂܂܂��Ǝ��ɂ܂��v�ƌ����āA��э��݂Őf�Ă��炢�A�������˂Ɩ�����܂���āA������悾��𐂂炵�Ȃ������߂��������Ƃ�����܂��B
�s����ł�ŕ|���̂́A�Փ��ɑ��邱�Ƃ��Ǝv���܂��B��C�ɉ����������Ǝv�����Ƃ��ƁB
����́A���������ł��B�����ė~�����ł��B
�ǂ��������Ă��������B
��肭�A�h�o�C�X�ł����ɁA�\����Ȃ��v���܂��B
yuko����̏�Ԃ������Âł��߂��Ă���邱�Ƃ��F��܂��B
�܂��A������ׂ肵�����ł��ˁB
����܂ł́A
�o����Ƃ��ɏo���邱�Ƃ��o���邾���B
����ł́A���炢�����܂����B
 yuko
yuko  2023/07/22(Sat) 00:53 No.28396
2023/07/22(Sat) 00:53 No.28396
���������������߂Ȃ��Ă��߂�Ȃ����B
���X�A�ق�ƂɐS�����ł��B
 yuko
yuko  2023/07/29(Sat) 15:29 No.28398
2023/07/29(Sat) 15:29 No.28398
���́��ʂ͕̂|���̂ŁA���̓_�����͑��v�ł��B
 �ڂ���
�ڂ���  2023/07/30(Sun) 22:29 No.28399
2023/07/30(Sun) 22:29 No.28399
������������������Ă��܂��B
���������������߂Ȃ��̂́A�ǂ������C�ɂȂ���Ȃ��ł��������B
�O���͗N���ĂȂ��Ƃ������ƂŁA���S�v���܂����B
�ł��A�[���T�̋ꂵ�݂́A�ς�����̂�����܂��B
���̒m��yuko����́A�����I�Ȉ�ۂȂ̂ŁA�قڐQ������Ə����Ă���̂����āA�܂������ƂɂȂ�Ȃ��Ɨǂ��̂����c�ƁB
�ŏ��̓��e�͕K���ŏ����ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�������Ƃ��G�l���M�[���g���܂�����ˁB
��킭�A���ȊO�̕��ɂ��Ayuko����̋L���Ƀ��X�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A���������Ă��܂������߂ɁA���̕��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ȁH�Ȃ�āA�[�ǂ݂����肵�Ă��܂��܂����B
�l���������ȁB
���h���Ǝv���܂����A�ǂ����������������v�킸�ɂ��Ă��������ˁB
����ւ̕ԐM�͂��C�ɂȂ���Ȃ��đ��v�ł��B
�����������Ɍf�����g���ēf���o���Ă��������ˁB
�������s���܂��傤�I
�ڂ���
 yuko
yuko  2023/07/31(Mon) 16:51 No.28400
2023/07/31(Mon) 16:51 No.28400
�������c���C���NJ撣���Đ����Ă܂��B
���߂Ă̓��@�c�s���ł����ς������ǁA�����ɗ�����B���撣���Ă����A�����撣��܂��B
�ڂ��������ꂽ���X��ǂ�ŁA����������Ȃ��Ǝv���܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
 �ڂ���
�ڂ���  2023/07/31(Mon) 22:03 No.28401
2023/07/31(Mon) 22:03 No.28401
�傫�Ȍ��f���Ǝv���܂��B���͓��@�ɑ��Ă��s��������Ǝv���܂��B���͑ΐl�ɂ��X�g���X�������₷���l�Ԃł����̂ŁA���܂�����Ă����邩�A�ƂĂ��s���ł����B�ł��A������X�g���X���痣��Ď��Âɐ�O�����yuko����̌��f�͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ����������ƋC�������x�߂ė��Ă��������ˁB
�w�������c���C���NJ撣���Đ����Ă܂��B�x�Ə����Ă���܂����B
yuko����͐�y�ł����A���́A�uyuko����A�G���������ˁB�v�ƌ����Ă��������ł��B
�v���N�����ƁA���̓��@�����́A�l�K�e�B�u�Ȉ�ۂ͂���܂���B�搶���S���m���e�g�ɂȂ��ăT�|�[�g���Ă���܂������A�����A�����獷�����ޗz�̌��Ŗڂ��o�܂��A�P���̏I���ɗD�����[�Ă��ɕ�����a�@�̑�����̂��ޕ��i�́A�ƂĂ��S�𗎂������Ă���܂����B����ɋC�Â��܂łɂ͏����̎��Ԃ�v���܂������B
���́A�s���Ǝv���܂��B
�a�@�ł̏o��⎡�Â�yuko����ɁA�ǂ����ʂ������炷���Ƃ��F��܂��B
�ڂ���
 �ς��
�ς��  2023/08/01(Tue) 10:15 No.28402
2023/08/01(Tue) 10:15 No.28402
�ς�ςƐ\���܂��B���̃T�C�g�̉��̕��ł肳����ƃ��b�Z�[�W�̂��������Ă��܂��B
�킽���͗\��ł�7��31���ɐ��_�a���ցu�C�ӓ��@�v�ƌ����`�Ō����������Ă���u���a���v�ɓ��@����\��ł������A�}篂��̕a���Łu�V�^�R���i�̊����ҁv���o������8��9���ɓ��@�͉�������܂����B
���_�������́u�o�ɏLJU�^�v�ŏ����O�܂Łu������ԁv�ɋꂵ�߂��A�[��U�K���ă}���V�����̍�ɏオ�莩�E�����݂悤�Ƃ��āA��������Ɛ^�����ŃR���N���[�g�̒n�ʂ��������A���̎���ɕԂ��āA��э~�莩�E���|���Ȃ��߂ĉƂɋA��܂����B
���̌���O���͑�������Ԃ����Ȃ舫���킽������搶�ɏ����b�����ē��@�������ӌ���`���Č��݂Ɏ���܂��B
���_�a���̌��w�������Ă��炢�܂����B�Ō�t�l���̋߂��ɂ͌����u�F�m�ǁv�̕��������A4�`5�l�̑啔���͏o���邾�������a�C�̊��҂������Ă���݂����ł��B��������̂ł����L���ŁA�啔���͖����ł��B
�����ɂ���ĕς��̂ł����A���z�×{��ȕ��S�z���x�z�ƌ������x������܂��B������g���Ɛݒ�z�ȏ�͂����͗ǂ���܂���B�A���H����A���̎g�p��͑ΏۊO�ł��B
�㎝��������������܂��B��{���E�Ɏg��ꂻ���Ȃ��́i�R�A�K���X�A�C�ށi���C�^�[�Ȃǁj�A�A���R�[���ށj�킽�����������̂̓X�}�z���������֎~�ł����B(*_*)
YUKO����̏������݂�q�������Ƃ���A�u�ڂ����v����A�h�o�C�X������Ă���̂Łu�ڂ����v����̃A�h�o�C�X�ŗǂ��Ǝv���܂����A
�t��������Ƃ���Ɓu������ԁv�ł̎��E��}�̔������́A������Ԃł͊�����Ԃ�120�{�ȏ�B����Ԃł́A������Ԃ̖�60�{�Ƃ̃f�[�^�[������܂��₽�瑽���ł��B
�{���ɑo�ɐ���Q�̒��ł��킽���͍ł��댯�ȏ�ԂƎv���Ă܂��B�킽�����u������ԁv�̎��Ɏ��E�����݂����Ȃ��̂����Ă��܂��B���͓����z�����݂����ł����A�܂��܂��������݂͂����A�N����܂���B�قڐQ������ł��B�ł����̎��������@�̋@��ƍl���܂����B
yuko����@���炭�u������ԁv�̎��͋C���͗����āA�O��������ɂ�������炸�A�ő�����A�₯�ɏՓ����������Ȃ������ł����H�킽���͂���Ȋ����ł����B�厡�ォ�烉�c�[�_�i�o�ɏǂ̂������P�j����������Ă܂������A��C��0�ɂ���܂����B�R���܂͂��Ƃ��Ə�������Ă܂���B
yuko����@�킽�������_�a���ɓ��@���܂�(+_+)
�o����ΒZ�����Ԃł�������Ȑl���m��̎��ł����A���F�B�ɂȂ肽���ł��B
�킽����8��9���ɔC�ӓ��@���܂��B�u�o�ɐ���Q�U�^�̂ς�ρv���
 �ς��
�ς��  2023/08/01(Tue) 10:40 No.28403
2023/08/01(Tue) 10:40 No.28403
��قǏ������݂����҂ł��B
������ԂɊւ��܂��āA���E��}�̕|���������܂��������̍�����
�Ȃ����T�C�g�����Љ�܂��B�ǂ���Ό��Ē�����K���ł��B
�o�ɐ���Q�́u������ԁv�ɂ��ďڂ��������Ă���܂��B
�t�q�k
https://sakura212.com/bipolar-disorder-100/9280/
�ς��
 yuko
yuko  2023/08/02(Wed) 20:24 No.28405
2023/08/02(Wed) 20:24 No.28405
�ς�ς���A�͂��߂܂��āB���S�z���肪�Ƃ��B�ł��A���͊O���͂Ȃ��āA���Ƃ������t����|���̂ł��B
����l�ցA�܂��F����ցA���̑�ςȕa�C�Ƌ��Ɋ撣���Đ����܂��傤�B
�Z�����X�Ŏ��炵�܂��B
 yuko
yuko  2023/08/13(Sun) 21:03 No.28408
2023/08/13(Sun) 21:03 No.28408
���@�O�Ƀl�b�g�œ��@�̌��L��F�X���ׂĐk���オ���Ă���ł����A���ۂ͕��ʂ̗ǎ��I�ȓ��@�����ł����B
����̓��@�̖ړI��1�́A��ɉߕq�Ȏ��ɍ����������������邱�ƂȂ�ł����A�����l�q�����Ȃ���A���ޖ�E�ʁE�^�C�~���O�E�ڕ���F�X�����Ă܂��B
���Ljȗ������Ɠ���C�������ꂵ���āA���̍��₪�����������N�������̂��Ɛ�]���Ă܂������A13���ڂ̍����̓c�����C����������܂���B����ς�����̂������ł��B
�܂��܂��s����Ȏ����Ȃ̂ł��܂�y�ώ��͂��܂��A��]�̌����������C�����܂��B
�}����������ƏI������c�̂��ȁH�@�ł炸�ɁA
�F��Ȍ��̊Ō�t�����B�Ƃ��܂荇���āA��������(�ق�Ƃ͑����A�肽������)���Â��܂��B
�܂��́A���܂ŁB
 �ڂ���
�ڂ���  2023/08/16(Wed) 11:02 No.28409
2023/08/16(Wed) 11:02 No.28409
���@����ď����ǂ����𖡂킦�����ƁA�ǂ������Ȃ��ƁA�ǂ܂��Ē����܂����B
�ƂŐh���������ɏo���Ȃ��������ƂŁA���@���ďo����悤�ɂȂ������Ƃ͂���܂����H
�������A�������A�ˁB
�炪���Ƃ��A�����������B�ł��A�ǂ��Ǝv���̂ł��B�B�����𖡂키�ƁA�C�����ЂƂǂ����Ɍ������悤�Ɏv���܂��B
�������s���܂��傤�B
�ƁA�������g�ɂ������������Ă��܂��B
���A�T���ł��B
�ڂ���
 yuko
yuko  2023/08/18(Fri) 15:45 No.28410
2023/08/18(Fri) 15:45 No.28410
���@�O�͕|���Ȃ�قǐH�~���Ȃ�������ł����A������@2�T�Ԗڂł���ƒ��H�̃p�����g�[�X�^�[�ŏĂ��܂����B
�܂�A�Ă����p�����H�ׂ����āA���̊��҂���(���l�Ɖ�̂��R���C)�̂���H���܂ōs���Ă����̂ł��B
�����̓x�b�g�ŐH�����Ă��āA�g�C���ɍs���Ƃ��͎Ԉ֎q�������̂ł����A��������s��ɕς��܂����B
�S�̏Ǐ�ɔ�ׂĐg�̂͏����ɉ��Ă��āA���肪�����ł��B���������A�S(�])�̏Ǐ�����������Ăق����ł����A�ł�Ȃ��ł������{�����܂��B
����͕s�����������āA���ꂪ�T�������������܂łƈႤ�Ƃ���ł��B�ڂ�������͂��o���ςł���ˁB���̃c�����ɑς��Đ����ė���ꂽ���ƁA�ق�Ƃɑ��h���܂��B�������Ȃ��c�����撣��܂��B
 �ڂ���
�ڂ���  2023/08/19(Sat) 00:51 No.28411
2023/08/19(Sat) 00:51 No.28411
�Ă����p�����H�ׂ����Ȃ�����ł��ˁI
�������ЂƂ�ŕ|���Ȃ��H���܂ōs�����̂ł��ˁI
�q�l���|���r�͂ƂĂ��悭������܂��B
�����O��̓��@��2�����ԂŁA�������瑼�̊��҂���ɐ����������̂̓[���ł��B
�މ@���鍠�A�g�C���ł�������ɘb���������āA�Ђƌ��Ԃ����̂��A��b�̑S�Ăł����B
���̊��҂���̓��r�[�̂悤�ȏ��ɏW�܂��Ė�x���܂Ő���オ���Ă��܂����B
���͕|���Ă��������ւɂ͓���܂���ł����B
�u�{���ɂ��̐l�B�͓��@����K�v������̂��낤���H�v�ƂЂƂ���Ŏv���Ă��܂����B
�厡���Ō�t��S���m�Ƃ͐[����b���ł��܂����B
���̂��Ƃ����������b���܂��ˁB
���͍��AB�^��Ə��ɐȂ������Ă��܂��B
�{�[���y����g�ݗ��ĂĂ��܂��B
�܂�8���͑̒�������قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��̂ł����c�B
�����ł炸�����Âł��B
����͑��̊O�Ƀg���{�̌Q�ꂪ���܂����B
�Ȃz�����������Z���Ȃ����悤�ȋC�������܂��B
���l�����ς�炸�����ł����A�܂������炩�G�߂̈ڂ낢����������悤�ł��B
�㏭�����̍������䖝����A�H�����āA�R�[�g���H�D��G�߂�����̂ł��傤�ˁB
���̋������E�ɂ��A����Ȏ��ɂ��A�X���F�Â�����A���̃T�N�T�N���鉹�������ɖK��Ă���܂��B
�����ÂG�߂��ς��悤�ɁA�����ƕa����ς���Ă����Ǝv���܂��B
������x�Ί��yuko���߂�܂��悤�ɁB
�����ƁA�[��ł��B
���₷�݂Ȃ����B
�ڂ���
 yuko
yuko  2023/08/19(Sat) 09:33 No.28412
2023/08/19(Sat) 09:33 No.28412
�A���̖ҏ��̒��A��Ə��܂Œʋ��āA��ƂȂ����Ă�̂͂������Ǝv���܂��B
���͖����������x�̎����ł����Ƃ��Ă��܂��B�f�C���[���ɏW�܂銳�҂���B�Ƙb���������͂Ȃ��ł��B
���鎖�A�N���鎖�A�g�C���ɍs�����A�����C�ɓ��鎖�A�|���C���������߂������A���ꂾ���Ő���t�̖����ł��B
����Ȃ�őމ@���ĉƂœ�����߂������������̂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��܂����A��̎��͍l���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�����̒��œ�����߂����̂��܂���ςł��傤�ˁB�ǂ����A���̂ɋC�����Ă��߂����������܂��B
 yuko
yuko  2023/08/19(Sat) 14:10 No.28413
2023/08/19(Sat) 14:10 No.28413
�ŏ��ɏ��������_�ł́A�厡��ɍ�����Ԃƌ���ꂽ�̂ł����A���@��̈�t�͎��̗l�q��2�T�Ԍ��āA�����Ƃ������T�ƕs����Q�̏Ǐ����o�Ă���ƌ����Ă܂��B�����s���̋��|���������āA������o�ɐ���Q�̏Ǐ�Ȃ́H�ƕs�v�c�Ɏv���Ă܂��B
���ɕ|���̂����ʎ��Ȃ̂ŁA�O���̂��b�͂ł��Ȃ���ł��c�@�ς�ς�����ł͂Ȃ��āA�N������ł��ł��܂���B
�ڂ�������Ƃ͂��b���Ă�̂ŁA�Ȃ������Ȃ��Ƃ��v���̂ł����A���������a��Ȃ̂ŋ����ĉ������B
 yuko
yuko  2023/08/28(Mon) 19:58 No.28429
2023/08/28(Mon) 19:58 No.28429
�����ŏ��������X��ǂݕԂ��āA����ł́u��Ə��ɂقƂ�Ǎs���ĂȂ��v�Ƃ����������X���[���Ă�݂����ŋC�ɂȂ�܂����B�Ȃ̂ŁA�⑫�����Ă��������ˁB
���̍����̒��A���܂ɂł��s���Ă�����̂͂������Ȃ��A�Ǝv��������ł��B
���ꂩ��A�O�̗l�q�ɏH�������Ă�����`�ʂ�ǂ�ŁA�܂�Ŏ������l�ɂ���悤�ȋC�����܂����B
 �܂�
�܂�  2023/08/30(Wed) 08:09 No.28438
2023/08/30(Wed) 08:09 No.28438
������u�g��u���Ƃ��낪�Ȃ��v��ԁA�����J��Ԃ��o�����Ă��܂��B
�x�^�ȓ����Ƃ��ẮA�ڕ�������ŐQ���������邱�Ƃł����A���ꂷ��ł��Ȃ��̂��s����Ԃ��Ǝv���܂��B
���@�����f�������Ƃ́A�ŏI�I�ɂ͎����I��Ă�����i�ł��B���߂ĂƂ������ƂŁA����ɓ��ݐ���yuko����͂ƂĂ��E�C������Ǝv���܂��B
�f�C���[���ɍs�����Ƃ��E�C�����邱�Ƃł���ˁB���@���ɓ��@���Ԃ��ł��邱�Ƃ��A�s�������ɂȂ���܂����B
�g�̂̕��͗����������Ƃ������ƂŁA�S�̗����������ǂ����Ă���Ƃ����ł��ˁB
������莞�Ԃ������ė×{�ł���Ƃ����ł��B
 �ς��
�ς��  2023/09/21(Thu) 17:12 No.28440
2023/09/21(Thu) 17:12 No.28440
��ς��ꂵ���v���܂��B���@����6���N����9�������A���͂��傱����
�����J���ꂸ�A���������̃r�j�[���܂͎��E�Ɏg���Ȃ��l�Ɍ���
���J���J�����܂��B���͓�d�ł������Ă��܂��B�X�}�z�̎���
���݂͋֎~�œ����͍�ƗÖ@�m���s���J���I�P�≹�y�ӏ܁A���Q
�[���Ȃǂ��s���܂��ƁA���@���͊O�o�֎~�A�O����̖ʉ�͐e��
�����ł��B�ł����̋K�������������H�������I�ł����A���ꂪ�ǂ�
�����̂��A�މ@���ɂ͂قڊ�����ԂɂȂ�܂���('��')�U
yuko����@���@���͌ǓƂȂǃX�g���X�͊������܂���ł������H
�킽���͍ŏ��̂Q�T�Ԃ͎₵���Ď₵���ċ����Ă���ł����B
�N�Ƃ����b������C�Ɋ���܂���ł����B�ł��킽���̕a���͑���
���ł��̒��ł킽����菬���ȏ��̎q���H���ɗU���Ă�����Ă���
�����������Ƀg�����v�Ȃǂ��ď��X�ɂ��F�B�������܂����B�މ@��
�鎞�͗܂Ō������Ă��炢�܂����B�킽���͂��̓��@���C�ɍ�����
�Ԃ��犰����Ԃ܂ŋC���������オ��܂����Byuko���̌f����
�݂͂Ȃ����a�C�Ő���Ă����܂��Byuko����@�݂Ȃ���yuko
����̖����ł���B���݂����������ɕa�C�Ə��ɕt�������Ă���
�܂��傤��(*^��^*)
yuko����ց@�ς�ς��
 vogcopy.net
vogcopy.net  2023/10/13(Fri) 16:17 No.28446
2023/10/13(Fri) 16:17 No.28446
�T�J�C�̃f�U�C�i�[������o���́Ahttps://vogcopyrolexboy.blog.ss-blog.jp/ 2010�N�����3�N�ɂ킽�胂���N���[������W�J���ꂽ�R���{���[�V�������C���u�����N���[�� S�v����|���Ă����B���N�̓����N���[����70���N���}����Ƃ������ƂŁA�T�J�C�Ƃ̃R���{���[�V�����Ɏ������Ƃ����B
 �ς��
�ς��
�肳����A���q�������Ă��Ȃ����S�z���Ă܂��B
�킽���̕��͑��ς�炸�A��s����ł��B
�����킽���͈�l�ڂ����Ȃ̂ŁA�肳����̏������݂ł������~���Ă��܂��B�肳����A����������Ȃ��ł��������ˁB�����o�ɐ���Q�ł��B�C���̔g�͔��[����Ȃ��ł��B
���̕a�C�͖{���ɕ|���a�C�ł��B���R���E���������ł��B
�킽���͐l�Â����������ŁA���܂ł�������̂��F�B�������܂����B�����ǓƂŁA������ӂ߂܂��B
�肳����̏������݂����x���ǂݕԂ��Ă��܂�(*^-^*)
�����܂��~�܂�܂���B�肳����͂킽���̐S�̎x���ł��B
�����f��������A���߂�Ȃ����B
�肳����A�������݂͑̒����悢���ł��܂��܂���B
�����Ă���������܂���悤�ɁI�I
�ς�ς��A�肳�����
 �V��
�V��  2023/06/23(Fri) 07:30 No.28379
2023/06/23(Fri) 07:30 No.28379
�o��2�^�͓s���̂����悤�ɍ��ꂽ�a���Ƃ����ӌ�������܂��B
�x���]�W�A�[�s���̍R�s�����2010�N�̃l�C�`���[�Ƃ����G���Ńh�[�p�~���������邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�h�[�p�~�����������N��Ԃ̂悤�ɂȂ�A��ٔ������N����̂ł��B
���͉��̃x���]�W�A�[�s�������߂Ĉ��ނƁA�ϐ����o���ĂȂ��̂��N��Ԃ̂悤�ɂȂ����肵�܂��B
�x���]�W�A�[�s���őϐ����ł���Ƃ́A�M���o��e�̂ƃh�[�p�~����e�̂��������邱�Ƃ������܂��B
�o��2�^�Ɛf�f����A���_�Ȃ̖��f���C�ɂȂ�ꂽ��q����̃u���O��\��t���Ă����܂��B
���̕��͕������ڂ�����̂��ƂȂǕ�����Ă���u���O�ł��B
�@�@�@�@�@�@��
https://ameblo.jp/marron-masayo/
 �V��
�V��  2023/06/23(Fri) 08:27 No.28380
2023/06/23(Fri) 08:27 No.28380
�f�p�X�͔��������Z���̂ŁA�h�[�p�~�����T�b�Ƒ����āA�T�b�ƌ���̂ŁA���ʂ��������₷���̂ł��B
�܂��A�x���]�W�A�[�s���̕���ԗ��E�Ǐ�Ƃ����̂�����A���ɕs����Ńx���]�W�A�[�s��������ł���ƁA���ނƃh�[�p�~���������Ĉӗ~�I�ɂȂ邯�ǁA�x���]�W�A�[�s���̌��ʂ����Ɨ}���ɂȂ�����A�s���ő��������܂����肵�܂��B
 �ς��
�ς��  2023/06/23(Fri) 22:08 No.28381
2023/06/23(Fri) 22:08 No.28381
�������݂��肪�Ƃ��������܂����B�������Ɣq�ǒv���܂����B
������Ă܂��u�o��2�^�͓s���̂����悤�ɍ��ꂽ�a���Ƃ�����
��������܂��B�v�Ƃ͂ǂ������Ӗ��ł����H�킽���͓������a��
�f�f����܂������A�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ȃ炸�A�a�@��ς��܂����B����
�ĉ��߂ē����̑̒���C�����ׂ���1���Ԃ��炢�����Ē���������
�o�ɐ���Q�U�^�Ɛf�f���ꂨ����啝�ɕς��܂����B
�܂��V���l�����w�E�̃x���]�W�A�[�s���n�̍R�s���܂͈�؏�����
��Ă܂���B�����āu��q����̃u���O�v���q�����܂����B
���_�Ȃ̖��f���C�ɂȂ�ꂽ�̂ł���(*^-^*)
���̕������a����o�ɇU�^�Ɛf�f���ꂨ����������������
�����̂�f��Ō����ɕa�C����E�o����{���ɂ悩�����Ǝv����
���B
�������玄�̈ӌ��ł����A���Ȃ��͂킽���̑o�ɇU�^�̏Ǐ��f��
��Ă���̂ł����H
�킽���́u��Q�N���Q���v�u���_��V�Ҏ蒠2���v�����Ă�
���B
�������ꂱ��10�N���炢�ł��B�킽�����o�ɐ���Q�U�^�Ɛf�f����
�Ă����ł��B���̂킽���̏Ǐ��m���Ă��u�s���̂悢�o�ɇU
�^�v�Ǝv���܂����H�킽���̐��_�����͂������d���ł��B������
�킽���͔��ɑ@�ׂȐ��_�����҂ł��B���Ȃ��̌��t�Ŏ��E���Ă�
�܂���������܂���B
��q����̗l�ɒf��ŗǂ��Ȃ�ꍇ������A�����łȂ��l������
�����܂��B��T�Ɉꊇ�肳��Ȃ��ł��������ˁB
���ɂ�������Ă܂����A���Ȃ��̕��ʂ���͐S�̉����݂��܂�
�����������܂���B
�킽���͎��E���������@���o�����Ă܂��B���܂�킽��������ȏ�
�h������悤�ȏ������݂͂���Ȃ��ł��������ˁB
���肢���܂��B�E�E�E�E
��邿���̎��E�z�M
https://www.youtube.com/watch?v=YwvoxsEcnRM
 �V��
�V��  2023/06/23(Fri) 23:11 No.28382
2023/06/23(Fri) 23:11 No.28382
���A�d���ɏo������O�ɋ}���ŏ������̂ŁA�o��2�^�͓s���̂����悤�ɍ��ꂽ�a���̈Ӗ��������Ă��܂���ł����B
����͐����Ђ����̂ɓs���̂����a���Ƃ����Ӗ��ł��B
20�N���炢�O�ɂ��͂�����̕��׃L�����y�[���Ƃ����̂�����܂��āA�o��2�^�Ƃ������҂���ʂɑ����܂����B
�����Ō����s���̂����o��2�^�Ƃ́A�����Ђ������̖��̔����邽�߂ɐV�����o��2�^�Ƃ����T�O�����o�����Ƃ����Ӗ��ł��B
���ۑo��2�^�Ɛf�f���ꂽ�l�̒��ɂ́A�o�ɐ���Q�̕�������A��̉e���Ōy�N��Ԃ̂悤�ɂȂ��đo��2�^�Ɛf�f���ꂽ�l������Ƃ������Ƃł��B
�ς�ς���̂��̋ꂵ�݂͂悭����܂��B
���̏ꍇ�ł����ƁA�c�����̋s�҂���Ȍ����ł��a�ɂȂ��Ă��܂������A���{�g���[���A���A�ӂ�0.5mg�����ނ��ƂŁA�h�[�p�~����������ٔ������N�����A�N��Ԃ̂悤�ɂȂ��đo�ɐ���Q�ގ��Ǐ�ɂȂ��Ă����Ɨ�������Ɏ���܂����B
�ς�ς��A������̌f���ł����낪�������̂��肢�܂��B
 �ς��
�ς��
�N���������I�I�������ɂ����E�E�E�E�E�E�E�E
�o�ɐ���Q�Ǝ��E
�o�ɐ���Q�͂��Ȃ��ʓI�ł���A100�l��1�l���l���̂��鎞�_�őo�ɐ���Q�Ɛf�f����܂��B ���ׂẴo�b�N�O���E���h�̒j���Ə����́A�o�ɐ���Q�ǂ���\��������������܂��B
�o�ɐ���Q�̐l�́A���E�����݂���A���ۂɎ��E�����肷�邱�Ƃ�����܂��B���U�ŁA���҂͈�ʂ̐l��菭�Ȃ��Ƃ�15�{�����E�𐋂���\���������Ȃ�܂��B
�i�o�T�A�o�ɐ���Q�̃E�B�L�y�f�B�A���j
 �肳
�肳  2023/06/09(Fri) 19:40 No.28366
2023/06/09(Fri) 19:40 No.28366
�ς�ς����
���߂܂��āB
�������傤�Ǎ����炢����ł����B
���ɖ�͍����ɂȂ�₷���ł��B���͂P�^�X���ł����A�����̂��̓Ɠ��Ȃ炳���N���S�̂ɋ��ʂ̂悤�ł��ˁB
�Ƃ��Ɏ��ɂ����ȁA�ƟT�X�ƍl���邾���ł͂Ȃ��A�E�B�L�ŏ�����Ă���ʂ�A���E���������a�C�Ȃ̂ł����A�Փ�����������ԂȂ̂ł��킢�ł���ˁB
��Ԑl�ԊW�ł����Ȃ�̂��悭�킩��܂��B������Ԓǂ��l�߂���̂͐l�Ƃ̂������ł��B����Ȃ炳�����L�ł���l�����Ȃ�������Ƃ������A��X���܂��B
�ł������Ă����A���ɂ����Ǝv���̂��A�Փ���������̂��A���������C�����������ē��e����̂��A���ȕ\���̈�ŁA�炳����������ߒ��Ȃ̂�������Ȃ��Ɣg���d�˂Ă���Ɗ������肵�܂��B
�����������Ƃ����āA�Ɍ��̂Ƃ���ŁA�Ȃ�Ƃ���������ł��Ă��������A���ꂾ���H�v���Ă鎩���̂��Ȃ��Ăق߂Ă��������ł��B���ӎ��ł��E�E�E�B
�ƂĂ������ł��铊�e���肪�Ƃ��������܂����B
�܂����C�y�ɏ����Ă��������ˁB
�肳
 �ς��
�ς��  2023/06/11(Sun) 22:33 No.28367
2023/06/11(Sun) 22:33 No.28367
�N��Ԃ̍U�����E�C���C���E�Փ����ɉ�����āA����Ԃ̊O���Ɩ{���Ɋ�Ȃ���Ԃ����������Ă܂��B
�����Ă��̌f���ɐ����ȋC�����������܂����B�N���ԐM�Ȃ�Ė����Ǝv�����J���Č���Ɓu�肳����v����킽���Ɠ����悤�ɋꂵ��ł������������̂�������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�l�ԊW���Ă킽�������ł��B�a�C���痈��Ǝv���܂����A�O����͂킽���ُ̈�Ȑ_�o��Ԃ���݂�ȋ����Č����Ă܂��B
�肳����A�T�^�Ȃ̂ł��ˁB�{���ɂ���ǂ��Ǝv���܂��B�킽���͂��̐h���A�悭��������܂���B���݂��������Ȃ��l�ɂ��܂��傤�ˁB
�肳����̏������݂�ǂނƗ܂��~�܂�܂���I
������l�ڂ����ŁA�킽���Ȃ�Ă��Ďv���Ă܂����B
�{���ɖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�܂��C����������ł��܂��܂���B
������Ɓu������ԁv�Ɓu���E��}�v�̕���������܂����B
�\��t���܂��ˁB���Q�l�ɂȂ�B
�u������ԁv�Ɓu���E��}�v�ɂ��Ă̌������Љ�܂��B
National Institute of Health and Welfare�̌����ŁA�o�ɏǂ̂�
�܂��܂ȃt�F�[�Y�ɂ����鎩�E��}�̔����ɂ��Ē����������̂�
���B
�E5�N�Ԃ̃t�H���[�A�b�v���Ԓ��ɁA718�l�̊��҂�90���̎��E��}�@�@�@������
�E���E��}�̔������́A������Ԃł͒ʏ�C����Ԃ�120�{�ȏ�B���a�G�s�\�[�h���ł́A�ʏ�C����Ԃ̖�60�{
�Q�l�FPallaskorpi S, et al. Bipolar Disord. 2017 Feb 8.
���E��}�́A������ԂƂ��a�G�s�\�[�h���ɑ����A������Ԃł͂��N����₷���悤�ł��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���a�G�s�\�[�h���A�N�a�G�s�\�[�h����
�����Ǐ����Ȃ������m�F���邱�Ƃ͏d�v�ƌ����܂��B
�ς�ς��A�肳�����(*^-^*)
 �肳
�肳  2023/06/11(Sun) 22:41 No.28368
2023/06/11(Sun) 22:41 No.28368
�܂��{���͌���������Ē����܂��ˁB
�̒��̊W�ŋT���X��������܂��A��낵���ł�(o^^o)
�@
�肳
 �ς��
�ς��  2023/06/14(Wed) 15:56 No.28371
2023/06/14(Wed) 15:56 No.28371
�o������ԐM��]���܂��B
�����ЂƂ�ڂ����̂ς�ς��B
 �肳
�肳  2023/06/14(Wed) 17:53 No.28372
2023/06/14(Wed) 17:53 No.28372
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł���B
�����̒��̊W�ł��Ԏ��ł��Ă��Ȃ��āA
�ق�Ƃɂ��߂�Ȃ����ˁI
�ŋ߂͍������Ȃ��A�����������ǁ[��Ɨ}����������ԑ����Ă�����Ċ����ŁA�Ȃ��Ȃ����͂��܂Ƃ߂�͂��Ȃ��āB�����̒��I�Ɋ�{�͍��������Ȃ̂ł���ɂ��Ă̓��X��������������ł��B
�������������Ԃ���������K���ł��B
��낵�����˂������܂��I
�肳
 �ς��
�ς��  2023/06/14(Wed) 20:52 No.28373
2023/06/14(Wed) 20:52 No.28373
�̒����ǂ��Ȃ����ŁA�킽���ɏ������݂��������āA���肪�Ƃ��������܂��B
�킽���́A�肳�����S�̎x���ɂ��Ă��܂��B
���q���ǂ��Ȃ�ꂽ��A���ł��������݂��҂����Ă��܂��B
�������b���������ł��B
�肳����ւς�ς��
 �肳
�肳  2023/06/16(Fri) 12:17 No.28374
2023/06/16(Fri) 12:17 No.28374
���Ԏ����x��Ă��߂�Ȃ����I���͑̒��������Ɠ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��āA���͂���肭�������A���Ԏ����T���X�ɂȂ肪���ɂȂ�Ǝv���܂��B�O�����Ă��߂�Ȃ����ˁB
�ς�ς���̕��͂����ɂ��Ԏ��������Ă��������܂��ˁB�u���v�ׂ̗����̂��Ԏ��ł��O�O�F
���̎����������������܂��ˁB�o�ɐ���Q�͂���10�N�ȏ㊳���Ă܂��B�厡�ォ��̓��`�E���E�f�p�P���E�Z���N�G���E���c�[�_�E���ܑ��Ŗ�15�����炢����ł܂��B�킽�����u������ԁv�ƌ����āA�搶����ȑO���珈������Ă��R���܂̃��c�[�_����C��0�ɂ���܂����B��{�o�ɐ���Q�ɂ́A�R���܂͗ǂ��Ȃ��݂����ł��B
���������c�[�_����������Ă��܂���B���܂肨��͏ڂ����Ȃ��̂ł����A�����ׂ��烉�c�[�_�͍R���_�a��i���W���[�g�����L���C�U�[�j�݂����ł��B�ł��m���ɂ��̒�グ���ʂ�����܂���ˁB���͎��̓��c�[�_���������ꂽ�Ă̎����N�]���Ă���œ��@���邱�ƂɂȂ�܂����i�O�O�G�j�ł������Ђǂ��̂Œ������Ă�����Đ搶�̔��f�ŏo���Ă�����Ă��܂��B
�������N�]�̈�킾�Ǝv���̂Œ�グ���ʂ����邨��͈����Â炢�ł��ˁi�G�G�j
�N��Ԃ̍U�����E�C���C���E�Փ����ɉ�����āA����Ԃ̊O���Ɩ{���Ɋ�Ȃ���Ԃ����������Ă܂��B
�����ꂱ���������ł���ˁi�G�G�j���͍����̎��͐Q��������̂ł����A�����������Ă��̂܂܂��ƐQ��Ȃ��̂œڕ����g���܂��B������܂����W���[���g���܂��ˁB
�����Ă��̌f���ɐ����ȋC�����������܂����B�N���ԐM�Ȃ�Ė����Ǝv�����J���Č���Ɓu�肳����v����킽���Ɠ����悤�ɋꂵ��ł������������̂�������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
���l�Ƃ��ď������Ă��������Ă���̂ōŏ��̏������݂ŐG��Ȃ������̂ł����A���͎��͂��̃T�C�g�̉^�c���i�����Lj��j�Ȃ�ł��B�{���͊F����ɂł��邾�����Ԏ��������̂ł����`���ɏ������悤�ɍ��͂��܂�S�̗]�T���Ȃ��āi�G�G�j���߂Ă��߂�Ȃ����ˁB���Ȃ݂Ɏ����Lj��݂͂�ȓ����҂Ȃ�ł���B
�l�ԊW���Ă킽�������ł��B�a�C���痈��Ǝv���܂����A�O����͂킽���ُ̈�Ȑ_�o��Ԃ���݂�ȋ����Č����Ă܂��B
���悭���ԂƘb���Ă����̂́A���̕a�C�͕\�����́u�܂Ƃ��Ȋ�v���ꐶ�����U���āA����̂܂܂̎��������炯�o�����Ƃ��ł��Ȃ���˂��Ă��Ƃł��B���ɒ����N�G�s�\�[�h�ŌǗ��������ł����A����̂܂܂̎����Ƃ��ĊO�̐��E�ł͐����ł��Ȃ��āA�X�g���X�ɂȂ�܂��B�ł������������_�̃f�B�[�v�ȃ��x�������L���Ȃ��ƌ��S�Ȑl�ԊW�ƌ����Ȃ����A����҂ł������f����Ă��鐢�̒������A���ꂪ�ł��Ȃ����̒��̕��u�ُ�v�Ȃ��I�ƋC�Â����̂����̕a�C�œ����Ă悩�����C�Â����Ȃ��Ǝ������܂����肵�܂���
�肳����A�T�^�Ȃ̂ł��ˁB�{���ɂ���ǂ��Ǝv���܂��B�킽���͂��̐h���A�悭��������܂���B���݂��������Ȃ��l�ɂ��܂��傤�ˁB
���P�^���Q�^���Ǐ�͑����Ⴆ�ǁA�h���̂ɂ͕ς��Ȃ��ł���ˁB�ς�ς�����������Ȃ��ł��������ˁO�O
�Ō�ɂ��߂ɂȂ镶�����肪�Ƃ��������܂��I�����ғ��m�ł����A�����Ƃ����̂͂��܂�F�m����Ă��Ȃ��̂ŁA�����ƍL�܂�����Ȃ��Ǝv���܂��I�Ԃ����Ⴏ��Ԑh���Ǐ�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��E�E�E���������悤�ɓ��Ɋ댯�ȏ�Ԃł����ˁB
���E�ɂ��Ăł����A�����͂��̏�Ԃɒǂ����܂ꂽ���͐����鉿�l�Ȃ����Ďv������ł��܂��̂ł����A���Ԃ�����������ƁA�����Ȃ��ƂȂ��I���ĐS����v���̂ŁA���Ԃւ̑z���������̋��Ƃ��č��܂Ŗ{���ɋ~���Ă��܂����B
��������k�����Ő̂قNJ��C���Ȃ��āA�\����Ȃ�����Ȃ̂ł����A�ߋ��̏������݂�ߋ����̕W�ihttp://bipolar.ac/kanto/report/report.html�j���Q�l�ɂ��Ă���������A���Ԃ̐��������邩�ȂƎv���܂��B
����Ƃ��ǂ�����낵�����肢���܂��O�O
�肳
 �ς��
�ς��  2023/06/16(Fri) 18:24 No.28376
2023/06/16(Fri) 18:24 No.28376
�������݂��肪�Ƃ��������܂�!(^^)!
�������Ɠǂ܂��Ē����܂����B�肳���A���̃T�C�g�̎����Lj��ƕ�����������u�A�Ђ��܂������A���e��ǂ�ł���Ƃ��l�����悭������A���S���܂����B
�����āA�ߋ��̏������݂�ߋ����̕W�������ǂ݂܂����B����ȕW�ł���(*'��'*)
���ꂩ��������Âǂ�ł����܂��ˁB��Ȏ������肪�Ƃ��������܂����B
���ꂩ�����낵�����肢���܂��B
�����܂ł��O�u���ŁA������{��ɓ���܂���(*^-^*)
������ƈÂ����b�ł����A�킽���͐����O�A�u������ԁv����Ȃ�
���A�O�����ɂ߂č����A����͕s�����Ǝv���A�ڕ�������ŁA
�Q�悤�Ƃ��܂������A���ꂸ�A�N����Ȃ̂������ڂ݂��A�O��p
�j���Ă܂����B
���̓��A�ӂ��Ǝ��ɂ����Ȃ��āA�߂��̂U�K���Ẵ}���V�����̃G
���x�[�^�[�ɏ��ŏ�K�ɒ����A���̗x���̍��ɗ����A���E��
�悤�Ƃ��܂����B��̏�ɗ������ĉ�������Ɛ^�钆�ʼn��̃R���N
���[�g�������Ȃ��ŁA�|���Ȃ��ĉ�ɕԂ莩�E����߂܂����B
������ƑO�ɂ������܂������A���E��}�́A�o�ɐ���Q�́u������
�ԁv�̐l�Ɓu������ԁv�̐l�Ɣ�r�����120�{�ȏ�Ƃ���܂���
���l����ƂȂ�قǁI�I�Ǝv���܂����B
�܂��A�o�ɐ���Q�̎��E���́A����҂̎��E����20�{�ȏ�Ƃ̐���
����A�����āA�o�ɐ���Q�̐l�̎����͌���҂���10�N�Z������
�ł��B�����͐��_�Ȉォ��̍����̂�����ł��B
����ς�A�o�ɐ���Q�̂킽���͕|���a�C�������Ă���Ƃ��Â�
�v���܂��B
�����炱���A�킽���ɂ́A�肳����̑��݂��傫���ł��B
�����ЂƂ�ڂ����Ŏ₵���ł��B
���F�B�����l���܂������A�N��Ԃ̎��ɂ��낢����f�s�ׂ���炩
���A�܂�����Ԃł̃h�^�L�����������A�����Ă����܂����B
����A�葊���݂Ă��炢�܂����B���̌��ʁA�킽���͂������̐l
�ƈႤ�Ǝv���Ă��܂��H�ƌ���ꂻ���ł��ƌ����ƁA���Ȃ�
�́A�ϑԂ��Č����܂����B�܂�����̐l���ώ@���߂��āA������
�����Ă��܂��āA�����͂����䂤�����ōs���Ƃ����Ȃ�Ƃ��l���A
�s�����肪�o�Ă��āA��Q�ϑz�œ��������ς��ɂȂ�A�����ł�
�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��H���ƌ����܂����B�����ł��B���ƌ�����
�����B�����Ă������N���`���Ɛ��_��Ԃ͕s����łȂ������ł�
���H���Ǝw�E����܂����B�����ł��A�ƌ����܂����B
�����܂œ��Ă�Ȃ�`�`���Ǝv���܂����I�I(^-^;�@
����Ȏ葊���炢�ŕ�����̂��Ė{���ɕs�v�c�ł��B
����͎��E�����Ǝ葊�肢�ɂ��ď������Ă��炢�܂����B
�肳����@�܂��킽���̂����肵�Ă���������ꂵ���ł��B
����Ȃ킽���ł����X�������肢���܂���(*^-^*)
�ς��
 �肳
�肳  2023/06/18(Sun) 12:30 No.28377
2023/06/18(Sun) 12:30 No.28377
����A�W�Q�l�ɂ��Ă��������ˁB
���E�Փ����������̂ł��ˁB���h�������ł��ˁB
������N�̔N�����������ȁA����������Ƃ��Ă���R�b�v���ۂƂ�Ɨ��Ƃ��āA���̂܂܃}���V�����̍ŏ�K�܂ōs���܂����B
�s�v�c�Ƌ����Ȃ������̂ł����A������������̎�������l�̂��Ƃ�z��������A�������̕��ɂ����Ƃ��Ďv���Ƃǂ܂�܂����B�i���X�����Ă��߂�Ȃ����j
�^�钆�Ɉ�l�ł��钆���S���邱�Ƃ͕|���ł���ˁi�G�G�j���������̑z���ł����A���E���Ăق�ƏՓ��ŁA���s����l�͂������f�Ƃ��̈ӎ����āA�Փ��ɕ������Ⴄ�����Ȃ̂���Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂��B�����܂Œǂ��l�߂��Ȃ��悤�ɓ��X�ӎ����Ȃ��ƂȂ��Ǝv���܂��B
������������A�Ȃ����ł����N�Ǝv���Ă�����̂������������Ƃ����l�͑����Ǝv�����A���E�����������D�ɗ����܂��B
����ȋt�s���悭�����Ă��ꂽ�ȂƁA�����Ɋ��S�����Ⴄ���Ƃ�����܂��i�j
�ǓƂ͓����҂̉i���̃e�[�}�Ɏv���܂��B���Ȃ��Ƃ����͂����ł��B
���Ƃ��l�Ɉ͂܂ꂽ���������Ă��Ă��A���S�������Ă��炦�Ȃ��A������Ă����������Ȃ��ƐS�̒��ł͏�ɌǓƂȂ̂������҂Ȃ̂�������܂���B
�����瓯�a�҂̑��݂͑傫���ł���ˁB
�肢�A�������낢�ł��ˁB
�肢�͂��Ă����Ȃ������̂ł����A�ȑO�肢�t�̕��Ƙb�������Ƃ������āA������~�߂�ꂻ���Ȑl�ɂ̓l�K�e�B�u�Ȗʂ������邯�ǁA���͌�����m��Ȃ�������肭���������݂����Ȑl�ɂ͂����ē`���Ȃ��Ƌ����Ă���܂����B
�Ƃ������Ƃ͂ς�ς���͂����Ƃ����g�̏�Ԃ��悭��������Ă���Ǝv��ꂽ�̂��Ȃ��Ȃ�āi���O�O���j
����������Ă��āA�������ł��ˁI
�f���P�[�g�ȓ��e���������ɘb��������Ď��炵�܂����B�ł͂ł́i���O�O���j
�肳
 �ς��
�ς��  2023/06/19(Mon) 16:41 No.28378
2023/06/19(Mon) 16:41 No.28378
�킽���́A�肳���A���܂�ď��߂ďo�����S�̎x�����Ǝv���Ă܂��B
�킽���͂���܂ł����ς������ς��̐l���痠��ꂽ��A�������ꂽ�肵�Đl�Â������Ŏ��s���Ė{���ɋꂵ�������ł�(+_+)
�����킽���ɂ������͂���Ǝv���܂��B
�肳�����������Ă���l�ɁA�ǓƂ͉i���̃e�[�}���Ƃ킽�����v���܂��B
�u���Ƃ��l�Ɉ͂܂ꂽ���������Ă��Ă��A���S�������Ă��炦�Ȃ��A������Ă����������Ȃ��v�Ə�����Ă��鏊�͖{���ɋ������܂����B
�����瓯�����_�����̂肳����ƒ��ǂ��������̂ł��B���ꂩ������`�`�`�`�`�`���Ƃ��肢���܂�!(^^)!
�킽���͐肢�ł�����ꂽ�悤�ɁA�������̐l�Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���Ă��Ȃ����Ǝw�E����A�肢�t�͏��Ȃ���A���Ȃ��͕ϑԂł���ƌ���ꂽ���̓h�L�b�Ƃ��܂���(+_+)
�ŋߖ����̂悤�ɁA�肳���狳���Ă�������u�W�v��ǂ�ł��܂��B
�����������ł�����e�E���ɂȂ���e�������A�܂�����������܂��u�N�T�̉�v���s��ꂽ��A�Q���������ł��B
�肳����@�u������ԁv�̒��A�N���Ɏ��E�������ꂽ�̂ł��ˁI
�����������̋C����������܂���B
�킽���͂T��20���̖����Ɏ��E�������܂����B
�킽���̏ꍇ�́u����ԁv����u������ԁv�ֈڂ�܂����B
���������u����ԁv�ɂ��ւ�炸�A�ڕ�������ł��A�S�R�Q��ꂸ�����ɊO�o���܂����B
�������̎��͐��_��Ԃ͂��������Ȃ��Ă܂��B
�ӂ�ӂ�p�j���A�ӂƎ��ɂ����Փ��ɂ����A�C���t���ƃ}���V�����̍ŏ�K�̍�̏�ɗ����Ă܂����B
����э~��Ă����������Ȃ���Ԃł������A��������Ƌ}�ɕ|���Ȃ�A���s����߂܂����B
����Ȃ��b�́A�肳�����ł��܂���B���ꂪ�킽���Ȃ�ł��B
�����ЂƂ�ڂ����Ŏ₵�����X���߂����Ă܂������A
���͂肳����Ƃ��m�荇���ɂȂ��āA�S���������Ȃ�܂�(*^-^*)
���x���肳����̏������݂�ǂ�ŁA�����Ă܂��B
�킽���͐l���̂��犴���������������܂��B
���鐸�_�Ȉオ�u���̊댯�����鐸�_����5�I�v���������Ă��܂����B�ȉ��Ɏ����܂��B
�@���H�ǁA➁�o�ɐ���Q�A�B�A���R�[���ˑ��ǁA�C���E���p�[�\�i���e�B�[��Q�A�D����������
����ς�A�o�ɐ���Q���������Ă܂����B���������ǂ��ꂪ�����ł��B
�肳����A���݂��������_�����ł��A�|���a�C�ł����A���������ɕa�C�Ƃ��܂��t�������܂��傤��(*^-^*)
�킽���́A�肳�����S�̎x���ƍl���Ă܂��B
������Ƃ킽���̎��������܂��ˁB
�킽���́A��Q�N���Q���E��Q�蒠2���ŁA�Q�T�ԂɈ�x���_�a�@�Őf�@���A���Ɉ�x�J�E���Z�����O���Ă܂��B���\�A�Ǐ�͂������ł��B
�O�o���o���܂���B�����Ђ��������Ԃł��B
����Ȃ킽���ł����A�肳�����낵�����肢���܂�<(_ _)>
�ς��
 �ς��
�ς��  2023/07/02(Sun) 11:23 No.28383
2023/07/02(Sun) 11:23 No.28383
�킽���͂肳����̏������݂����邩�ǂ����A�������Ă܂��B����
���A�肳����̏������݂��Ȃ����ȁH����ς�̌J��Ԃ���
���B�킽���͂܂��ЂƂ�ڂ����ɂȂ����̂��H
���Z�����Ǝv���܂����A�o�����珑�����݂��肢���܂��B
�ς��
 �肳
�肳  2023/07/02(Sun) 12:12 No.28384
2023/07/02(Sun) 12:12 No.28384
���Ԏ�����ϒx��Đ\����܂���B
���͍��M���o���Ă��܂��āA��������藎�������Ă��܂����B���������肨�Ԏ��ł�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B
�ǓƂɂ��Ăł����A�����Ȃ��a�C���̂ɗ������Ȃ��Ȃ�����āA������Ȃ��Ă����傤���Ȃ��̂��Ȃ��Ǝv���ʂƁA�ς�ς���̂悤�ɐl�ԊW�̒��ł��̕a�C�̏Ǐ�̎��蔽��������ƁA�l���đ��҂ɖ��S�ŗ�������p�������Ȃ��̂����Ȃ̂��Ȃ��Ɨ��ʊ����邱�Ƃ�����܂��B�������l���m�������Ƃ��݂��̓��ʐ��E�ɊS��������Ή����ł�����̂�����͂��Ȃ̂ɁA�Ɣ��Ǔ����͂悭��������܂����B
�ϑԁA�ł����I�ł��Љ��O�ꂽ�Ƃ���͓��a�ҋ��ʂ��Ă���Ǝv���̂ŁA��ʓI�ɕς����̂Ɍ����邩������Ȃ��ł��ˁB�Y�o���Ƃ����肢�t����ł��ˁ`�I
�W��ǂ�ł����������肪�Ƃ��������܂��B�O�O�@�����k���Ō��݂͏W���͂���Ă��Ȃ��̂ł����A�O�ՂƂ��ĎQ�l�ɂȂ�ł��B
�����̃l�b�N�͐Q��Ȃ��Ƃ���ł���ˁ`�G�G���ɂ����C�����A���ɂ����ȏo�����A���L�ł���l�͓���ɂȂ��Ȃ����Ȃ��ł���ˁB���ɂ����C�����Ə����܂������A�ق�ƂɎ��ɂ����킯����Ȃ��āA������̂�����قǐh����ȁB�������Ⴆ�A�����Ɛ���������Ȃ��B�킽���B��������z���Đ����Ă���݂�Ȃ͂��炢�I�Ǝv���܂��B�i�Ȃ��������ɏƂ炷�ƂȂ��Ȃ������v���Ȃ��j
�N���a�͓��Ɏ��E���������ȋC�����܂��E�E�Փ��������邩��ł����ˁH���܂蓝�v�ȂǏڂ����Ȃ��̂ŁA�ς�ς���̏������ݎQ�l�ɂȂ�܂��B
���������͂ς�ς���Ɠ����ł��O�O�@�Ǐ�͏d�������Ǝv�����ǁA�����X�p���ōl����Ƃ����Ԃ������Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B�܁A�f�f�ȑO�́A�������łȂ����N���a�́u���v�̎����m��Ȃ������ߋ��Ɣ�r���Ăł����ǂˁi�O�O�G�j
�܂Ƃ܂�̂Ȃ����͂ł��߂�Ȃ����B���ƋT���X�Ő\����Ȃ��ł��B
�����Ȃ�܂������A�ǂ������������������ˁB
�肳
 �ς��
�ς��  2023/07/02(Sun) 21:34 No.28385
2023/07/02(Sun) 21:34 No.28385
�{���ɏ������݂��肪�Ƃ��������܂�(*^-^*)
�킽���͂����ЂƂ�ڂ����ł����A�肳��������̂ł���
��l���Ⴀ�A����܂���{���ɂ��ꂵ���v���܂��B���肪�Ƃ�����
���܂�<(_ _)>
�킽���͂�����ƑO�܂łƌ����Ă��A5�����܂Ő��_�ȃf�C�P�A
�[�ɒʏ����Ă܂����B�ł����̒��ł��킽���͂����ǓƂŁA����
�ꂵ���Ă��܂�܂���ł����B�����ĕs�������_�ɂȂ�A���̂���
�ɁA�j�����t�ŁA���������U���ȕ����f�C�P�A�[�X�^�b�t�ɓn����
���ʁA�厡�ォ��f�C�P�A�[�ʏ����֎~����܂����B���e��������
��Ȃ��U���I�ł��A����������̎����u�킽���v����Ȃ��A�j����
�g���u���v�Ƃ����ď����܂����B�Y�t�t�@�C���Ɏ����܂����B�肳
���Ԃ�����Ƃ��ɂł��ǂ�Œ�������K���ł��B
�肳���ǓƂɂ��ď�����Ă�̂�ǂނƔ[�����܂����B
�������͏��w�Z�E���w�Z�ƕs�o�Z�ł����B���̐l�Ƃ��ւ�������
����Ȃ��̂ł��B�������C�ŁA�����������E���āA������C�ɂ�
�Ă���ŁA���̊Ԃɂ������߂̑ΏۂɂȂ�A���w�Z�ł͂�����
�������߂Ă��鏗�̎q�ɑ�������A���̎q�ӊO�̏��̎q�Ƙb���ƁA
�������炵�āE�E�����i�������ł��j�͂���10�������炢������
�Ȃ��āA���̎q�̃|�P�b�g�ɓ����I�I������E�E�E������
�������̂��̂�I�I���̏��̎q�Ƃ͐�ɘb���Ȃ��̂ɂȂ�����
��I�I
���v���A���̎q���ُ�Ǝv���܂����A�����͔��R�ł�������邪
�܂܂ł����B����Ől�ƃR�~���j�e�B�[���o���Ȃ��Ђ�������ɂ�
��܂����B�����������Ă�Ƃ������͗}���ł������ɂ����v��
�悤�ɂȂ�A���_�ȂŐf�@���Ē����u���a�v�ƌ����܂����B
���ꂪ�������́u�o�ɐ���Q�v�̎n�܂�ł��B
���X�����܂��Đ\����܂���B�肳����@����Ȃ������ł�
���A���̂ĂȂ��ł��������ˁB
���肢���܂��B
�ς��
[�Y�t]: 15123 bytes
 �ς��
�ς��  2023/07/02(Sun) 21:42 No.28386
2023/07/02(Sun) 21:42 No.28386
�u��邿���̎��E�z�M�v�̉̎��ł��B
[�Y�t]: 16517 bytes
 �ς��
�ς��  2023/07/02(Sun) 21:49 No.28387
2023/07/02(Sun) 21:49 No.28387
���ꂪ�킽���͒j�����t�ŏ������u�U���I�ȕ��v�ł�
���̒��ɂp�q�R�[�h������܂��B�����悯��X�}�z�̂p�q�R�[�h
�ǂݎ��A�v�����_�E�����[�h�����Ȃ��Đ�����܂��B
�悯��A�����Ē�������ꂵ���ł�(*^-^*)
���������j�����t�ɂȂ����̂͂��̕���������������������ł��B
�ς��
[�Y�t]: 22157 bytes
 �肳
�肳  2023/07/04(Tue) 16:33 No.28388
2023/07/04(Tue) 16:33 No.28388
�ς�ς���A�N���G�C�e�B�u�Ȃ̂ł���^_^
�ڂ�ʂ��̂ɂ����Ԃ��������Ǝv���܂�����낵�����肢���܂��Bm(_ _)m
���}�����炵�܂��I
�肳
 �肳
�肳  2023/07/11(Tue) 21:38 No.28389
2023/07/11(Tue) 21:38 No.28389
���Ԏ����x��Ă��Ă��߂�Ȃ����B
�������������Ԓ�����ƍK���ł��B
���߂�Ȃ����ˁB(><)
�肳
 �ς��
�ς��  2023/07/12(Wed) 19:30 No.28390
2023/07/12(Wed) 19:30 No.28390
�O��̏������݂́A���X�Ə�������ł��܂��āA�܂Ƃ܂�̂Ȃ���
�e�ł��߂�Ȃ����ˁB
�肳����@�킽���̏������݂��C�ɂ�����������Œ����Č��\�ł�
��(*^-^*)
������N�T�a�Ɗw�Ɛ��сi�m�\�j�̊W�ŋ����[�����e�̘_������
�����̂ł��m�点���܂��ˁI�P���u���b�W��w�̘_���ł��B�X�E�F
�[�f����15�`16��71���l��16�N�ԁA�ǐՒ����������ʁA�`����c�̊w�Ɛ��т̂����`�̐��т̐l�̒����N�T�a�̐l�����ɑ����A�_
���̌��_���N�T�a�̐l�́A�ɒ[�ɐ��т��ǂ��l�������A�܂��ɒ[��
���т������l������Ƃ̎��A��r�Ƃ��āu���������ǁv�̐l�͊w��
���т͈����l�������ƌ������ʂł��B�����N�T�a�͈���������
���Ǝv���Ă܂������A��������҂����ɒ[�ɗǂ��݂����ł��B
����͓V���̃P���u���b�W��w�̘_���ł��B�M�ߐ��͑傢�ɂ����
�v���܂��B
http://panpa2017.kir.jp/�u�N���a�v�ƒm�\�̊֘A.mp4
�����悯��Ό��Ē�����ƍK���ł��B
�S�̎x���̂肳�����
�ς�ς��('��')�U
 �ς��
�ς��  2023/07/12(Wed) 19:42 No.28391
2023/07/12(Wed) 19:42 No.28391
���߂�Ȃ����B
�t�q�k��ς��܂����B
http://panpa2017.kir.jp/ken.mp4
 �ς��
�ς��  2023/07/19(Wed) 15:10 No.28392
2023/07/19(Wed) 15:10 No.28392
�킽���@���������ǁA�a�C�̋ɒ[�Ȉ������厡��Ɂu���@�v����
���������Ǝv���Ă܂��B���܂ł���ȉ��̂Ƃ肦���Ȃ��A�l���m��
�ŁA�Ђ�������̂킽���ɑ�������Ă��炦�āA�������݂�������
����炢�{���ɂ��ꂵ�������ł��B�Z�����Ԃł������{���ɂ��肪
�Ƃ��������܂��B���悤�Ȃ�(*^��^*)
�肳����@�킽���͍�����@������̎��͔����ł��B
�ς��
 �肳
�肳  2023/07/21(Fri) 13:01 No.28394
2023/07/21(Fri) 13:01 No.28394
�����������̂ł��ˁB���@�ŋC���������₩�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB���@�͊O�̃X�g���X���Ւf����̂ňꎞ�I�ɂł��Ȃ�܂��A�l�I�ɁB
���������A���Ԏ����x���Đ\����܂���ł����B�ŋߔg�̋N������r�I�������Ȃ��āA�Ȃ��Ȃ��A�A�A���͂�����Ƃ��C���ł��B
�ǂ������厖�ɂȂ����Ă��������ˁB���߂Ă��肪�Ƃ��������܂����I
�肳
 �ς��
�ς��  2023/08/01(Tue) 10:55 No.28404
2023/08/01(Tue) 10:55 No.28404
���@�̌��ł����A�{����7��31���Ɂu�C�ӓ��@�v�̌`�œ��@����\
��ł������A�}篂킽���̓��@����a���Łu�V�^�R���i�̊����҂�
�o���v����8��9���ɓ��@�͉�������܂����B���}��������
���B
���q�̕��́u����ԁv���܂��Ђǂ��O��������A�厡��̐�
������u���̓��@�ŗǂ����悤�Ƃ���ڕW�́H�v�ƕ�����u�O
���O���v�������Ȃ鎖��ڕW�ɂ��Ă܂��v�ƌ����܂����B
�u�C�ӓ��@�v�Ȃ̂Ő搶����o���邾���{�l�̈ӎv�d���܂���
�����܂����B�l�`�w�͌����R�J���Ƃ̂��Ƃł����B
�F�X�����܂������A�܂��肳����@�̒����悭�������݂��o������
�Ȃ�܂��킽���̑�������Ē�����K���ł��B
�킽���͂����ЂƂ�ڂ����ł��B�������݂͉����t���ł͌�����
����܂���B�肳����̃y�[�X�d���܂��B
�ς��(*^-^*)