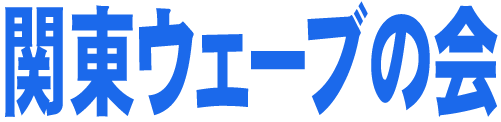�肳
�肳 2011/09/09(Fri) 16:59 No.257
2011/09/09(Fri) 16:59 No.257
����ɂ��́A
�N���a�c�̂̃X�^�b�t���Ƃ����ӎ����������̂��A���_��Q�Ƃ����A���_�[�O���E���h���E���甲���o���āA�n�㐢�E�i����҂����ς��̑�w�j�ɂ̂��̂��Ɣ����オ���āA�Ȃ�Ƃ��ڏZ���悤�Ɠw�͂��Ă����肳�ł��i�Љ���O�O�G�j
�ł��A�_���ł����B�����ۂ߂Ă܂��A���_�[�O�����h�ɖ߂��Ă��܂����E�E�E�B
��₱�������^�t�@�[�͂�߂�ƁA�Ƃɂ�����w�������s���܂����B�����N���X��S�����Ƃ��āA�����Ɉ�w���̐��k�ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B��w������܂��߂�邻���ł����A���M�͂���܂���B
���a�҂̕��X�Əo����āA�ΐl�W��d���i�c�̂̃X�^�b�t�Ƃ��āj�������肱�Ȃ���悤�ɂȂ��Ď��M�����Ă����̂ɁA�Ȃ�������҂̐��E���ƁA�a�C�̏Ǐ�ɉ����Ԃ���Ă��܂��܂��B
��w�ɓ������u�ԁA�l�Ԃ��ς�����悤�ł��B�A�p�V�[�Ǐ�Ǝ��͌Ă�ł��܂����A�����Ȃ��A�b���Ȃ��A�Ƃɂ����l�ԂƂ��Ď��R�Ȋ�{���y��\���ł��Ȃ��B�v�l��~��ԂƂ����̂ł��傤���B
�����A�|���̂ł��傤���B�������g�w�Z�͏��������납���D���ŁA���ł���w�ɍs���̂͊y�����̂Ŏc�O�ł��B�����Č����A�������y���݂ɂ��Ă�����Ȃ̂ɁA�Ȃ�������I�ɂ��̊��Łu�a�C�̏ǏЂǂ��Ȃ�v�̂��|���ł��B
�S���I�Ȃ��̂ł���A�J�E���Z�����O���Œ�����ʂ͂���Ǝv���܂����A�B��S���I�ȉ����͂��Ă݂�Ɓu�����̕a�C�̗������Ȃ����ɂ���ƕa�C����������v�Ƃ����R�l�N�V�����B�O���I�Ȗ��ł͂Ȃ��̂ŁA�������������炸�A����܂��B
�Ƃɂ����A�I�����C����w���ł���邩�A���邢�͐����ی���o�傷�邩�A����҂��R���g���[������Љ��{�݂Ŏ��R�Ɋ����ł��Ȃ��ꍇ�́A�����������ł��鐶�����A�ǂ����o���Ă������A�l���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
�������̐��N�ԁu�\���Z�E��w�E�o�C�g�ɍs���Ȃ���E�E�E�ł��s���Ȃ��v�̌J��Ԃ��ŁA�������Ă��܂��܂����B�{���ɂ炢�ł��i�����j������߂����Ȃ����ǁA������߂͂���Ӗ�����Ƃ��Ă��������܂��B
�Ƃɂ����A�ŋ߂̔Y�݂ł����B
��w���Ȃ����A�����Ƃ܂��݂�ȂƂ��b�Ƃ��������ł��i���O�O���j�݂�Ȃł�����Ă��������ł��ˁB��낵���I
�]�肳
 ������
������  2011/09/10(Sat) 17:12 No.261
2011/09/10(Sat) 17:12 No.261
��w�����ׂĂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ǁA�Ȃ낤�ˁA���̏Ǐ�H�̍��{�ɂЂ����Ă�����̂́H
���̃A���o�C�g�́A�I�[�v���Ȃ̂��ȁH
�N���a�c�̂̃X�^�b�t�Ƃ��āA���܂藝�����Ȃ��Ǝv����l�ȂǂɈ�l�Ō������肷��̂́A�Z�[�t�Ȃ̂��ȁH�i���̏ꍇ�A����͎������N���a���ƔF�����Ă���Ƃ����_�ł͋C���y�Ȃ̂��ȁH�j
�Ƒ��A�ގ��ȂǁA�ƂĂ������̐[���l�̂��𗣂�āA������x����������l�Ɉ͂܂ꂽ���͂ǂ�������ԂɂȂ肻�����ȁH
�i�肳����̏ꍇ�A�K���Ƃ��A�K����Ȃ����Ƃ��͕ʂɂ��āA�Ⴆ�Εa�@�̃f�C�P�A�Ƃ��H�j
�ȂA����U�߂ɂ��āA�ꂵ�������Ă��܂�����A���߂�Ȃ����B�ꂵ�������瓚���Ȃ��Ă�������ˁB
 ����[��
����[��  2011/09/10(Sat) 18:34 No.262
2011/09/10(Sat) 18:34 No.262
 �肳
�肳  2011/09/10(Sat) 23:47 No.264
2011/09/10(Sat) 23:47 No.264
�����ۂ���̎���́A�J�E���Z���[���v�킹����e�ŁA�M���ł��邼�B
�����������ۂ�����u�����U�߁v�ɂ������Ȃ��̂Łi�j������ƍl���Ă��炨�������܂��ˁB�S�������Ă���āA���肪�Ƃ��B���ꂾ���ł��������ꂵ���ł��i���܂Ŗ��S���Ĕ����̕���������������E�E�E���Z�E��w�̂Ƃ������Ƃ�������ǁj
����[������������
����A�ŏ��ǂƂ��u����[�v���ď����Ă������Ǝv���āu�Ȃ�[���O�ς����ȁv�Ǝv���Ă����i�ΕʂɎ����{�邱�Ƃ���Ȃ����ǁB���t���e�Ƃ������A�������O�ύX�e�H�j
���肪�ƁB����[�i���̕\�����g���Ă݂��������j
�]�肳
 �Ȃ�
�Ȃ�  2011/09/11(Sun) 11:06 No.265
2011/09/11(Sun) 11:06 No.265
��w���P�w��������Ȃ������Ƃ̂��ƁA�c�O�ł����ˁB
�ł����a�҂̒c�̂ł������M�͖{�����Ǝv���܂��B
����Ƒ�w�ɍs���̂͊y���������Ƃ��B
������{�����Ǝv���܂��B
�Ђ���Ƃ��Ă肳����͑��l�������̕a�C�𗝉����Ă���邩����Ȃ��������Ȃ�C�ɂ��Ă����܂��H
�����̌o������͑��l�͈ĊO�����������Ƃ͂���ȂɋC�ɂ��Ă��Ȃ��悤�ł��B
�݂�Ȏ����̂��ƂŎ��t�Ȃ̂ŁB
��w�ł͕������邱�Ƃ������ς�����܂���ˁB
�a�C�̗�������������ɋC�������邱�Ƃ͓���ł��傤���B
�������瑼�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������n�߂��Ȃ��ł��傤���B
��w�ɍs���̂͊y�����Ƃ̂��Ƃł����̂ŁA�������Ƃ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����̃X�^�b�t�����Ă̎��M�Ƃ��킹�āA���������ꂽ��܂���������o�����ꂽ��ǂ����Ǝv���܂����B
��w������߂邩�ǂ����͂��̌�l����ꂽ��Ǝv���܂��B
 ����[��������
����[��������  2011/09/20(Tue) 20:17 No.276
2011/09/20(Tue) 20:17 No.276
 �}��
�}�� 2011/09/09(Fri) 01:32 No.253
2011/09/09(Fri) 01:32 No.253
�͂��߂܂��āI
�e����D���ȃ}���Ɛ\���܂��B
���k�A�X�������肢�v���܂��B
�Ƃ���u���O�ł��̌f����`���b�g�����邱�Ƃ�m��܂��o��قNJ����������Ă��܂����B�����悤�Ȍo�������ꂽ�l�Ƙb�������ƐɊ���Ă��Ă��A�N�������Ă���ƂȂ�ƍ����ł͎����O���[�v�������Ȃ��Ȃ�������Ȃ����̂ł�����B
����ɏZ��ł���̂Ŋ֓��Ŏ��X�𗬂���Ă���F���ƂĂ��A�܂����v���܂��A�B�ƁA�����ɐϋɓI�ɕa�C�Ɛڂ���p���X�y�N�g���Ă��܂��B�ߋ��̋L����ǂ�ƕ������Ė���Ă��܂��B
�F����̏ꍇ
���̕a�C������閘�̑O�����ȐS�̓����������ė~�����ł��B
�˘f����ꂵ�݂�
�ǂ����z���Ă��܂������H
���̏ꍇ�O�����ɍs���Ȃ���Ɓu�V���b�N�v�ɊW�����ĉ߂����Ă����̂ł����A�Ƃ��Ƃ��W���J���Ă��܂����B��肫��Ȃ��v���ʼn߂����Ă��܂��B�����K�����̎v�����甲���o����������ł��B
�o�߂����������܂��ˁB
�ܔN�قǂ���Ԃł悤�₭�͂��������[�B
�t�ɒ���忂��悤�ɂƂĂ������I�ɂȂ�܂����B
���������N�قǑO�A���߂��N��ԂɂȂ���@���܂����B�N�Ƃ����Ă����̒��ł��s�����������̂œ��@����̂͐g�̂̕s���Ƃ���B�މ@���ĎO�����o�������ɉƑ��Ɏ��̐^����`�����A�V���b�N�ł͂���܂������Ĕ���h�����Ƃ��g�ɂȂ�Ȃ��O�ɖڗ�����������q���g�ɑ����낤�ƍ���ɂ��đ傢�ɘb�������܂����B
�ʉ@�Ń��[�}�X�A�ȂǂȂǂp�����݂ɓ���܂��B
�W���J���Ă��܂����������̍��B
��͂�U��Ԃ��Ă݂Ă�
���f���|���Ă��܂������ƂȂ������̂������
���ł����̎��̂Ȃɂ����������낤�B�B
�܂��������o������܂���B
�p�����������Ƃɔ��Ȃ��ł��Ȃ��̂ł��B�B�B
�厡��H���y�N��Ԃ����������ł����Ƒ��Ƃ��Ă��N��Ԃ̉����̂ł��Ȃ������悤�ł��B�l�ɑ��ĐS��z���Đ������Ă����Ǝv���Ă������Ƃ����̂��̂����Ƒ��l�̌��������S�R�Ⴄ���Ƃ��V���b�N�łȂ�܂���B�T���h��������N�̌���h���̂ł��ˁB�x����Ȃ������ƌǓƂƂ������̂������܂����B
�u�ō����ɏオ���Ă������炵�傤���Ȃ��v�Ƃ̐�������܂�
�B�������A�d�o���������͎����ƕ����Ă���̂œd�b��莆�ŎӍ߂��Ă܂��܂����B���l�Ƃ������A�قڑ�Ȑl�X�ɔ�Q������Ă����̂ł�����B�B���̂̒m��Ȃ��A�������|���āA�܂��ʂ̌�����������Ȃ�A�ʂ̐l�i�̎������̒m��Ȃ��Ԃɉ������Ă���悤�Ȋ��o�ɂ����ׂ�s�v�c�ȕa�C���Ɗ����Ă��܂��B
��]��
���ꂽ���Ȃ��Ƃ����v����
�V���b�N�������N�����Ă��邱�Ƃ͏��m���Ă���܂��B
�F������˘f�������������A�������|���Ȃ������A�ǂ�����ē��W�𗧂Ă܂������H
���̕a�ɂǂ�ȈӖ�������̂��낤���A�܂��܂������͌�����܂��l�Ƃ��Č����ɐ����Ă������ł��B��̑�l�������ŋ߂͋����Ă���ł��B�{���͂ƂĂ��ƂĂ����邢�}�����A��
 �݂���
�݂���  2011/09/09(Fri) 15:10 No.256
2011/09/09(Fri) 15:10 No.256
�͂��߂܂��Ăł��B
����ݏZ�̃}�����A�߂��Ⴍ����A�����܂����`�ł��B
�a�����Q�O�N�߂�����܂����A�S�R�����Ȃ点�܂���B
�N��Ԃ̎��́A�a���������ƌ����̂��a�C�ł��̂ŁA
�}�����g�A���i����l�ɋC�����Ă����ɂ��ւ�炸
�V���b�N���������́A�悭�悭�킩��܂��E�E�E
��ȕ��X�ɁA���ӂ��邨�莆���o����Ă���Ȃ�A�[���ł���B
�������ĉ�������͂킩���Ă���邵�A�������͗���邵�B
���̕a�́A���ɂ̊w�тƎ��͍l���Ă��܂��B
�����ɐ����Ă������炱���A�a�C�ɂ��Ȃ��Ă��܂����̂����A
�������M�����Ȃ��悤�Ȏ���l�l�ɂ��Ă��܂��E�E�ƌ���
�V���b�L���O�ł����A��̃R���g���[����
�����������Ԃ́A�܂������Ȃ��Ă����܂��B
���̕a�C�̑����̒��Ԃ����́A
�}������̂悤�ȑ̌������Ă��܂����B
���̂������́A�Q��Ȃ��Ȃ�B
�����̎g�������h��ɂȂ�B������ׂ�ɂȂ�B
��]�͂��Ȃ��ŁB��]�����Ȃ����ǁB
����̖��邢���Ђ��܂𗁂тĂ���A
���̓����A������悤��
�}������̐S�̔g��
����̊C�̂悤�ɉ��₩�ɂȂ����
����͂��ł����B
 �݂���
�݂���  2011/09/09(Fri) 18:26 No.258
2011/09/09(Fri) 18:26 No.258
�A���p�J����D���Ȃ݂����ł��B
��������烊�A���ɂ��ł���ˁB�i�Ɂj
�������������ł��ˁB
 �}��
�}��  2011/09/12(Mon) 11:20 No.266
2011/09/12(Mon) 11:20 No.266
���Ԏ����������ł��B���肪�Ƃ��������܂��B
�a���Q�O�N�݂̂�������̕���
�u���̕a�͋��ɂ̕a�ł��Ǝ��͍l���Ă��܂��v
���x�����x���������Ă��܂��܂����B
���ꂩ��F�����ꏭ�Ȃ��ꓯ���̌������ė����̂ł��ˁB
���̒�����݂����[����Ƃقڎ����悤�Ȃ��̂ł����B
�����̑��z�͔��ɓ˂��h����悤�Ƀ`���`�����܂��B�ł����甖��ł����Ă܂���A�B���̑��z���ŋ߂͉��₩�ɂȂ��Ă��ĊO�̋�C���N���N���N���B��������H�߂��Ă��܂����B�e��A��ċ߂��̍L��ł������Ȃǂ��ė���ł��܂��B�A���p�J������t���t���̖тȂ���ł������ꏏ�ɁA�B
�o���k�A�D�����A�h�o�C�X�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�����ŐF�X�F����̃R�����g�����ĕ������ĉ������ˁB
�݂�������Ɋ��ӂ����߂āB
 �݂���
�݂���  2011/09/12(Mon) 15:42 No.267
2011/09/12(Mon) 15:42 No.267
�ǂ��ł�����B���ł��A�����Ȃ点�Ă��Ȃ��ł����A
���̍��̐S�����l����ƁA�C�����������A�C�y�ȕ�����
�������܂����B������
�}������ɂ���]���ė~�����Ȃ��̂ł��B
�}������̕��͂���A
�Ȃ�ƂȂ��̂�т肳��̖����n�Ȋ������`���܂��B
�����A�̂�т�ł��B
�ł��̂ŁA�̂�т�̓���������
�̂�т莞�Ԃ��߂����Ă�����
�����Ƃ����Ԃł���B��Q�O�N�������Ƃ����Ԃł����B
��y���炵�āA�w�тƕ\�����Ă��܂��܂������A
�w�сB�Ƃ��������悤���������������ł��B
����ł́A�킩��Ȃ������A�����Ȃ��������E��
��R����܂����A���₵���o������R���܂����B
�}��������A�������������ʂɐڂ���@���������
����́A�w�тȂE�E�E�ƁB
�����͂������̓��ł��ˁB�i�e����̋��ꏊ�́j
������H�߂��Ă��܂����`�֓����H�߂��Ă��܂��B
�������܂͈�ł��B
����ŁA�S�ׂ���������܂��A
�����������Ă��钇�Ԃł��B
�܂낳��A���̂����A�Ȃ�Ȃ����`
�i�������s�K��������\����܂��i�Q�Q�j���j
 �}��
�}��  2011/09/12(Mon) 22:13 No.268
2011/09/12(Mon) 22:13 No.268
�݂�������
��������O���X�Ŏ���Ȃ��Ƃ�
�~�u���̕a�͋��ɂ̕a�ł��Ǝ��͍l���Ă��܂��v
���u���̕a�́A���ɂ̊w�тƎ��͍l���Ă��܂��v
�Ԉ���ď����Ă��܂��܂����B
�S���ʂ̈Ӗ������ɂȂ��Ă��A�A
��ώ��炵�܂����B
�_�l������������Ȃ��
���̕a�łȂɂ�`���悤�Ƃ��Ă���̂��낤�ƁA�A��]���ł����ς��ŏł���̂Ȃ�Ƌ������������Ă��鎄�B�N���܂ނƂȂ�Ƃ܂��܂���N�̕a�����Ȃ����B���̊ԁA�������ď�Ȃ��Ēp���������o�������Ă��܂������A�݂�������̒��������r���ɕ���悤�Ȍo����N���ɔ�ׂ�ΐ�]�Ȃ�Ă��Ă��܂����ˁB�u����́A�w�тȂA�A�v�����S�ɍ��݂܂��B����҂�������L��v����A�h�o�C�X�ł��A�B
�����͂ƂĂ������l��ῂ����L���C�ł��B
�֓����猩���邨���l�������Ă��邱�ƂƎv���܂��B
���������������̂ł���ˁB
����I
�Ȃ�Ȃ����[�������Ă��܂���B�哖����B
�݂�������ǂ������m�ł��ˁB
�P�Z���Z���Ɠ��`��ɂȂ�܂���B
�u�Ȃ�Ƃ��Ȃ邳�v�u�ǂ��ɂ��Ȃ邳�v�ł��B
���͂̂�т肳��Ɍ�����̂ł��ˁi�j
������������܂���A�e���D���Ȃ̂�����ǐ��N�O����T�y�[�X�ł��̂ŁB�A���p�J�̂�т��y�Ɋ��ӂ̋C�����ł����ς��ł��B
���Ȃ݂Ƀ��o����D���ł��B
�͋����ėD�����ڂ����Ă��邩��ł��B
�p�J�b�p�J�b�p�J�b�B
�܂��ł��ˁA�݂�������B
 �݂���
�݂���  2011/09/19(Mon) 12:50 No.270
2011/09/19(Mon) 12:50 No.270
�������o��D���ł��B
���N�O�A��������l�Ɠ������ŁA
�u�݂����́A���o�Ɏ��Ă�Ȃ��`�v
�Ȃ�Č����ėL���V�ɂȂ�������
����܂����B�i�j
���o�ƈꏏ�ɏ����������R����
�T�d�ɂ������ƕ��������ŁE�E�E�B
�܂��ł��ˁ`�}������I
 �}��
�}��  2011/09/23(Fri) 13:32 No.279
2011/09/23(Fri) 13:32 No.279
�ӂӂӁ@����I�Ɍ��Ă܂���[
�i�{�����Ȃ���������Ē����Ă܂��̂Łj
���o�Ɏ��Ă���Ȃ��!!!
�ō��ȖJ�ߌ��t�B
�ŁA����������炸�Ɏ~�߂��݂�������̎��_���A�B�X�e�L�B
�d���ו������Ă郍�o
�D�����D�������o
�̂̓��b��G�{�ɂ��o�ꂵ�܂����̂ˁB
���o�̖��́A���X�B
�݂�������u���{�[�ł��B
�͂����܂��ł��ˁB
 �}��
�}��  2011/09/23(Fri) 13:39 No.280
2011/09/23(Fri) 13:39 No.280
 ����
���� 2011/09/08(Thu) 10:15 No.249
2011/09/08(Thu) 10:15 No.249
�͂��߂܂��āB�N���a�Ɛf�f����Ė�P�N�́A����i�j���S�O��j�ł��B
�f������͂��N���a�������炵���A���E���Ă��܂��B
����ԕs���Ȃ̂́A���܂ŎЉ��Ƒ������������̂ĂȂ��ł��Ă���邩�ł��B���łɌ��̂Ă��Ă���C�����܂��B���ꂪ�A�����ƐS�̒�ɓb�̗l�ɂ��܂葱���āA�����̖������ƂĂ��Â����̂Ɏv���āA�ꂵ���ł��B
���݁A���[�}�X��400mg����ł��܂����A�^�ǂ����������Ƃ��Ă��A�ꐶ���̕a�C�Ƃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��ˁB�����āA���N�Ȏ����͂����߂��Ă��Ȃ��B
�݂Ȃ���́A�ǂ̂悤�ɂ��Ă��̕a�C�Ɛ܂荇�������āA�����Ă�����̂ł��傤�B������낵��������A������������������Ə�����܂��B�Ԃ����Ȏ���ł��邱�Ƃ͏��m���Ă���܂��B�����A�ꂵ���ɕ����Ă��܂������ŁA�A�B
 dango
dango
���́A�����������B���N�T�O�ɂȂ�܂����B
�a�����m�肵���̂́A�S�O�㔼�B�ł��A�P�O�ォ��A�����Ǝ��ɂ��������ł��B
���̕a�C�Ɛ܂荇�������Đ����Ă���l�Ȃ�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
������́A�f�p�P���W�O�O�ƃ��[�}�X�W�O�O���ƁA����ȊO�ɂ��Z���N�G���A�G�r���t�@�C�A���������܁A����p�~�߂ƁB�B�B��ł�������t�ɂȂ肻���ł��B
������ƌ����āA���q���ǂ��킯�ł��Ȃ��A�E�c�`�Ƃ��Ă���A�N�Ńx���n�b�s�[�ɂȂ�����A�Z�����ł��B
���ɂ����a�i�O���j�ɂȂ�Ɩ��ŁA�F�X���ł������������킯�ł��B�ł��A��������ĕ��͂������Ă���Ƃ������͍��A���̎��́A���͐����Ă���̂ł��B
�m���ɁB
�ꂵ���Ė��l�ł݂��Ƃ��Ȃ��āB�B�B����ł������Ă���B�B�B���˂Ȃ�����ł��B
�|������Ƃ������́A�u���ʁv�ɂ͉���������Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�_�l�̋��ƌ������A����Ȃ��́B
����̍��̋C�����B�T�������炷�}�C�i�X�v�l�ł͂���܂��H
���́A�����N���c���Ă��āA�y�������ł��B
�ŋ߂����@���Ă��āA�T�̐l���N���Ȃ��ĉ������B�B�B�Ȃ�Ďv���Ă��܂������炢������B
���[�}�X�A�f�p�P���̂��A�ŁA�N�Łu�������`�����v�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B
����́A�������Ƃł��ˁB
����Ƌx�{�Ǝ����̐����̃o�����X�������Ɏ�邩�ł��傤���ˁB�B�B�����͈Ղ��Ȃ�ł����i�j
 �R��
�R��  2011/09/08(Thu) 21:04 No.251
2011/09/08(Thu) 21:04 No.251
����Ƃ͈Ⴄ���Ƃł����ˁB�l�͉Ƒ��ɂ��̕a�C���C�Â��Ă��炦�܂���ł����B���̋��嗣���ł��B��Ђɂ͂Ȃ�Ƃ��b�܂�č��̓A���o�C�g�Ŏg���Ă��������Ă��܂��B
�����ԋꂵ�����ł��ˁB��͐�����ɗ��邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�Q�l�ɂȂ�Ȃ������炲�߂�Ȃ����B
 ����
����  2011/09/09(Fri) 09:44 No.255
2011/09/09(Fri) 09:44 No.255
���̂悤�Ȕ��R�Ƃ����������݂ɂ��Ԏ����ǂ������肪�Ƃ��������܂��B���͂���ԂŁA�Ȃ�Ƃ���������x�Ȃ̂ł����A�C�����ƕa�C�ɂ��ĕ�R�ƒ��ׂĂ��āA�����ɂ��ǂ���܂����B
�S�̏�Ԃ����������ƕ������Ă��Ă��A�����̗͂łł��邱�Ƃɂ͌��E�������܂��B������݂Ȃ���A�h�ꓮ�������ɖ|�M����Ȃ���A�܂��͐����邱�Ƃ���n�߂悤�Ǝv���܂��B
�����ɗ��āA�P�l����Ȃ��Ǝv�����Ƃ��A�{���ɂ��ꂵ�������B���ꂩ����A�ł����낵�����肢�������܂��B
 �R��
�R��  2011/09/09(Fri) 21:02 No.259
2011/09/09(Fri) 21:02 No.259
 ����
����  2012/03/29(Thu) 14:23 No.367
2012/03/29(Thu) 14:23 No.367
���́A�ӂ����і����̐X�ŁA�ꂵ��ł��܂��B�����ł͔F�߂����Ȃ��̂ł��傤���A�������͟T��Ԃł��B�ƂĂ��s���ł��B
�����Ŏ��₵�Ă���A���N���������Ă��Ȃ������̂ł��ˁB���̊ԂɁA�����ł͂��낢��Ǝ��݂āA�Ȃ����������ė����̂ł͂Ȃ����ƁA�v���Ă����B���ꂪ�A�a�C�̔g�̒��ŁA�����オ�����艺�������肵�āA���Ăт��Ƃ̂Ƃ���ɖ߂��Ă��܂��Ă���B���̋��������ǂ��\�������炢���̂��킩��܂���B
�����ł��ˁB����ł������Ă���B�����̏u�Ԃ��B���ꂪ��ԑ�Ȃ��Ƃł���ƁA�v���܂��B�ł��A�ꂵ���ł��ˁB�����o���������炢�A�ꂵ���ł��B�N���ƁA�b�������B�N���ɁA�����肽���B���߂�Ȃ����B
 �肳
�肳  2012/03/29(Thu) 14:57 No.368
2012/03/29(Thu) 14:57 No.368
���v���Ԃ�ł��B
�������Ђǂ����ŁA����̐S���́A�ƂĂ������ł��܂��B
���ʐl�͐S�̊����ɒ��ʂ���ƁA��������z���Đ������āA�F�X������̂��������Ɗ�����B
�ł����̕a�C�������炷�����Ƃ����̂́A������u�����̐X�v��ʂ蔲���悤�ƂƂ��Ă��A���͂��邮����Ɖ���Ă��邾���ŁA�܂����̏ꏊ�ɖ߂��Ă���C������B����Ȏ���̂Ȃ��A�ڂ̑O���^���Âȗ��B���܂ɂ���ȋC�����܂��B
������߂ŁA���X����B���̐S����N���ɓ`�������āA�P�O�O�O�y�[�W�Ԃ����Ƃ��Ă��A���炩�̌��_�Ɏ���Ȃ��A�����̕����̘A�Ȃ�ɂȂ��Ă��܂��C������B�N�ɂ��`���Ȃ������������̂ȋC������B������A�N���ɂȂ��Ȃ����������߂��Ȃ��āA�ǓƂȊ����ŁB
�E�E�E�Ȃ�]�̂����܂�݂����ȃ��X�����Ă��߂�Ȃ����i^^;�j
�����A���������o�����邱�Ƃ́A�l���݈ȏ�Ȋ����A�𖾂��ɂ����ăS�[���������ɂ����������炱���A����قǂ̎��肪�K������Ǝv���܂��B�����̏u�Ԃ��A�������܂����o���Ă��Ȃ������ŁA�l���݈ȏ�̐S�̐��n�����Ⴍ���Ⴍ�Ɛg�ɒ����Ă���͂��B�����������Ƃ���A��ʂ̐l�ł͌o���ł��Ȃ����̈�u��厖�Ɏv����A�Ɗ����Ă��܂��B
���͂��̕a�C���瓦���̂�����Ȃ�A���̕a�C���牽�������Ȃ����A�ƍl���̓]�����ł��邾������悤�ɂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�Љ�I�Ɏア����ɂ���l�X�ɋ����ɋ߂��A�V���Ȋ��e�����萶�������ƂƂ��B
�����邤���m�A�����܂��傤�B�����ŏ����ĂĂ��ꂢ�����Ƃ�������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��ʂ�����܂����A����ł���A�����Ӗ��̂Ȃ������̖����Ɗ����ł͐�Ȃ��͂��ł��B
�]�肳
 ����
����  2012/03/30(Fri) 08:34 No.369
2012/03/30(Fri) 08:34 No.369
����Ȑ���������̂�������܂���B��Ȃ̂́A�����ɂ��܂���Ȃ����H���ʂȂ�A������M����Ƃ����Ƃ���ł����A������M���߂��Ȃ������܂���H
���́H���炯�̖����̐X�̒��B�ꏏ�ɕ����ĉ������āA���肪�Ƃ��������܂��B
 ����
����  2012/04/02(Mon) 18:52 No.371
2012/04/02(Mon) 18:52 No.371
���̐l����́A�Ȃ�ł������ʈ����Ȃ�ł��傤�B���̖��@�̗͂Ŏ��������~���ĉ������i���ӂ͂Ȃ��q�Ȃ�ł����A�Ⴂ�̂ł��j�B��i����́A�l�̂��ƂɌ������l����������A�ǂ��Ȃ邩������Ȃ���B���ɐE��T������H�ƁB
�����A�ڂ��͂��̑g�D�̒��ŁA�َ��ȃi�j�J�ɂȂ��Ă��܂����̂��ȁ[�ƍl������A�S�̉������[��Əd���Ȃ��Ă��܂��܂����B�l�͕a�C�ł��B�������ŁA�Ǐ���R���g���[���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�����Ǝ����Ă݂��܂��B����Ȍ��t�͂�������o�Ă��Ȃ��āB
�Â��b��ł��݂܂���B���ɓf���o����Ƃ��낪�Ȃ��āB
 ����
����  2012/04/02(Mon) 23:23 No.372
2012/04/02(Mon) 23:23 No.372
�ǂ����A�����œf���o���Ă��������B
����ŁA���C�������y�ɂȂ�Ȃ�E�E�E
�Ȃ��Ȃ��A�O������͉��肸�炢��Q�Ȃ̂ŁA����҂͎d���̃X�g���X������ڂ₢�Ă��܂����̂��ȂƎv���܂��B
�Ƃ���ŁA
���E��ł́A����́A��Q�̂��Ƃ��I�[�v���ɂ���Ă܂����H�i��Q��`���Ă܂����H�j
��Q�́A�����ɂ���Ă܂����H�i�N���[�Y�H�j
���̃I�[�v���E�N���[�Y�ł��ŁA���̏ꍇ�̕Ԏ����ς��܂����A�Ⴆ�Ζl�Ȃ炱�̂悤�Ɍ�����������܂���B
�E���������Ă��A��Q������̂ŁE�E�E
�E�Ȃ��Ȃ�������̂悤�ɗǂ��E��͖������̂ŁE�E�E
�E�����Ȃ�ł��A�ǂ��Ȃ邩�s���ł��傤�����Ȃ��ł��B
�܂��́A�����
�E�����܂���A�撣��܂�
�ł��傤���B
�w��������o�Ȃ��������t�x�́A����ł����Ǝv���܂��B
���Ƃ��A�������Ƃ��Ă��܂��܂���������Ȃ��A�ςȂ�����݂�����ꂩ�˂Ȃ������Ƃ��v���܂����B
�����́A�������ꂸ�������Ƃ͎v���܂����A
�E��ł̎��͂̔����ŁA�̒�������Ȃ��i�����Ȃ��j�悤
�̒��Ǘ��ɐS�����邱�Ƃ��F���Ă܂��B
�ڂ����A�o������܂�����B
�@�@���ݖ��E�ŁA�A�J�P�����̂����ł����B
 ����
����  2012/04/03(Tue) 06:36 No.373
2012/04/03(Tue) 06:36 No.373
�E��ł̓I�[�v���ɂȂ��Ă��܂��B�����A�o�ɐ���Q�Ƃ����a���ł͂Ȃ��A�K����Q�Ƃ������ƂŁA�������̋Ɩ���Ə����Ă�����Ă��܂��B���ꂪ�܂��A�ڂɌ����Ȃ��s�������͂ɕ�点�錴�����Ǝv���܂��B
��������̂��������ʂ�A�u������o�Ȃ��������t�v�́A����Ȃ��ėǂ������Ɗ����܂��B�����ɋ����v���b�V���[�ɂȂ��ĕԂ��Ă��邾���ŁA�܂��̒���������˂Ȃ��ł��ˁB
�����́A�����������̂Ǝ���āA���܂Œʂ�ɁA���̎����ɂł��邱�Ƃ��A���Ȃ������Ȃ��̂��ȁB���悭��l���Ă��Ă��A�a�C������킯����Ȃ����A�l���x�߂Ύ��͂ɖ��f�����邯��ǁA�\������������Ɩ��f������킯�ł����A�ň��̎��Ԃ��A�A�A�B�����́A�炢����ǎ����Ȃ���A�����܂Ŏ����̑̒��Ǘ��ɐ�O���܂��B
���肪�Ƃ��������܂��B
 ����
����  2012/04/09(Mon) 11:24 No.386
2012/04/09(Mon) 11:24 No.386
 ����
����  2012/04/18(Wed) 09:57 No.387
2012/04/18(Wed) 09:57 No.387
�ł��A����̃y�[�X�̔����ŁA����P�^�P�O�ł�������A�������A�������Ɛ����邱�Ƃ�ǂ��Ƃ��悤�B���炾�ɐ��ݕt�����u�s���a�v���A�������Ǝ������߂ɁB
 ����
����  2012/11/08(Thu) 07:56 No.732
2012/11/08(Thu) 07:56 No.732
�����ɏ�������ł���A�܂��P�N�Ȃ̂ł��ˁB�Ȃ��ƂĂ����Ă��܂��B�ł��A��r�I�C���͗��������Ă��܂��B���A�܂������Ă��邱�Ƃ��A�s�v�c�ł��B
�����ɏ��������A�l�͐��g�����s���Ȉł̒��ɂ��܂����B�������Ă��A�������Ă��܂����������Ȃ������B
�C�����͂ǂ�ǂւƌ������܂����B�������A���������Ȃ���A���҂Ƙb������悤�ɂȂ�܂����B����Ȑ܁A�Õ��ւƌ������r���ŁA�����ȍ��L�Əo��܂��B�ЂƂ�ڂ����Ŏ̂Ă��āA�����Ԃ�Ƃ��т��H�ׂĂȂ��悤�ł������A�u�l�͐�����v�Ƃ����������b�Z�[�W������Ă��܂����B�i�����j
 �肳
�肳  2012/11/08(Thu) 21:52 No.734
2012/11/08(Thu) 21:52 No.734
�����������Ă���A�ƌ�����悤�ȃn�b�s�[�ȏ�ԂłȂ��Ă��A���܂Łu�������т���v�̂��i�ςȕ\���ł����O�O�G���͂悭���̓�@-������A�Ɛ������т�-�@���g�������܂��j�����ꂳ�܂ł��B
�������͎��Ɨׂ荇�킹�̂悤�Ȃ����o�����邱�Ƃ������āA
���a�҂̕��́A���̋��̂悤�ȑ��݂Ȃ̂ŁA���̂悤�Ȍo�������z���Ă��������ƁA�Ȃ��قƂ�ǎ����̂��Ƃ̂悤�ɁA�ق��Ƃ��܂��B�����āA���̂Ƃ��Ă̊�]�ɂ��Ȃ�̂ŁA���肪�����ł��B
���Ǝ��Ƃ����̂��\����̂��Ƃ��āA
�����L�̏ے��Ƃ��ď�����Ă���悤�ɁA�u���v�Ɨׂ荇�킹�Ƃ������Ƃ́A�u���v�Ƃ������݂̋����A�d�v�������݂��߂��闧��ɁA�������͂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�炢���ł��A�ӂ��̐l�����߂����Ă��܂��悤�ȁA�����₩�ȍK�����E���グ�Ă��������ł��B�ڂ�ڂ�̎̂ĔL�̂悤�ȁi�j
������Ɠ�������Ă��Ȃ��̂ŁA�܂Ƃ܂�̂Ȃ����͂ɂȂ��Ă��܂��܂����B���X�͋C�ɂ��Ȃ��ł��������B�܂����������҂����Ă��܂��B
-�肳
 ����
����  2012/11/29(Thu) 15:24 No.760
2012/11/29(Thu) 15:24 No.760
���L�́A�����ɂƂ��Ă͐��ւ̍Ō�̊�]�̂悤�Ɏv���܂����B���̎q�L�����̂Ă���A�l�͂����������Ȃ��B�{�C�ł����v���܂����B
���L���ƂɎ����A��ƁA���R�̂��Ƃ��ȂɎ̂ĂĂ����ƌ����܂����B�ł��A����͎q�L�����̂Ă遁���������ʂƌ��߂Ă��܂����̂ŁA��Ȃɋ��ۂ��܂����B�����āA���e��ɘA��������A�����a�@�ɑ��k�����肵�āA���e��{���܂����B
�������A���e�͂Ȃ��Ȃ�������܂���B���͂���傫���Ȃ�A���ɂ͎��Ƃ̗��e�܂ŗ��āA���������߂āA����܂łɗ��e��������Ȃ�������A�ی����ŏ������Ă��炤�Ƃ��������܂����B����́A�l�����ʓ��ł�����܂����B
�l���N�T������ԂɂȂ��Ă��܂����B����������������Ȃ�A��������������܂����B���L�Ɠ�l�A���藈�鎀�������߂Ȃ���̐����B�s�v�c�Ɛ�]�͂��܂���ł����B�ł��A�X���X���Ɩ���q�L�̊������Ƃ�邹�Ȃ��āB����������ɂ����e�͌�����܂���ł����B
���e�����������̂́A�����M���M���ł����B�p�[�L���\���a�̕��e���A�̂̋L���������ɂ�����Ă����l��T���Ă��ꂽ�̂ł��B���ǁA�l�͊F�ɖ��f�������������ł����B
����̂��ƂŁA�l���S�̕a�C�ł��鎖�������Ƃ��ɍĊm�F���܂����B���́A���L�͂��������т��̂��A�f���ɂ��ꂵ���ł��B�����ɂ͂������̒���ς���悤�ȗ͎͂c���Ă��Ȃ��B�ނ��됢�Ԃ̂��ו��ł��B�ł��A���L�͐����܂����B���ꂪ��Q�������Ă��Ă��A�����Ă��Ă��ǂ��Ƃ������Ȃ̂��ȂƁA���������v���܂����B�ق�̏��������A�A�A�K���ł����B
 ������
������ 2011/09/06(Tue) 21:54 No.246
2011/09/06(Tue) 21:54 No.246
�F����͓��@���ꂽ���Ƃ�����܂����H
���A���@�����߂��Ă��܂����A����������܂���B�搶�́A��̒��߂ƃ��~�N�^�[���̓�������@�Ǘ����Ɉ�C�ɂ���Ă��܂������݂����Ȃ̂ł��B
�����x���݂����ɁA���@������Ȃ�悤�Ȑ��x���Ă���܂����H
 dango
dango
���i�̒ʉ@�ɂ́A�u�����x���v�������Đf�@��A���Ƃ��Ɉꊄ���S�ɂȂ�܂����A���@����Ƃ��ׂĂR���ɂȂ�܂��B�������A����ɍ��z�×{����x�z�F�肪�K�p����܂��B
�����ɑ��āA���ȏ�̕��S�͂��Ȃ��Ă����Ƃ������x�ł����B
�ׂ������͕�����܂���̂ŁA�����̌��N�ی��g���ɂ��₢���킹���������B
���@�A����������������܂���ˁB
���́A�P�T�N�قǑO�ɓ�������Õی��^�̋��ςɏ������Ă��܂��B
 ������
������  2011/09/10(Sat) 16:42 No.260
2011/09/10(Sat) 16:42 No.260
���X���肪�Ƃ��������܂��B
�I�t��ł͂����b�ɂȂ�܂����B
���z�`�A�����g�������Ƃ���܂��B
������āA�����߂��炾�ƁA���Ȃ肨���ł����A������̔��܂ł̓��@�Ƃ��́A�������C���ɂȂ�܂���˂��E�E�E�B
���́A���ǂ����������̂ŁA�ی��͓���Ă��炸�A�����ɂ��ł��B�A�E������A���߂āA����ی������ł����肽���Ǝv���Ă��܂����E�E�E�B
 ����
����  2011/09/24(Sat) 04:59 No.281
2011/09/24(Sat) 04:59 No.281
�@���@�G�����́A�ߋ����@�����͂���܂������A���Ǔ��@�����Ɍ��݂Ɏ���܂��B�ߋ���x�����@�������ƂȂ��ł��B
�i�Q�^���s�b�h�@�a���P�W�N�j
�@�@���@�����ˑ��̕a�@�ł̑�O�҈ӌ��i�f�@�j�˓��@���Ȃ��ĕs�v�̈ӌ����炤�ˎ��Ȕ��f�˓��@�����ɒʉ@�E���Âs
�Ƃ����v���Z�X�Ō��݂Ɏ����Ă܂��B���Q�l�܂�
�Ȃ��A�����x���A�蒠�A��Q�N���̏����x�͌��ݗ��p���ł��B
 dango
dango
���X�A���l�̂�����Ƃ����ԓx�Łu�����Ă��Ȃ����v�Ǝv������ł��܂��B
����́A�����Ɛ̂���B�B�B
�{���Ȃ�A�����̕����{���Ă�������ʂł��A�����v���Ă��܂��ĉ��̂��A�ӂ�Ȃ��ẮB�B�B�Ǝv���Ă��܂��̂Ő����������B
���߂���A�ӂ��������y�����炩�ȁB�B�B
 ����
����  2011/09/06(Tue) 20:08 No.245
2011/09/06(Tue) 20:08 No.245
�@�@�������ϑz�ł��ˁB�ł��A���ی����Ă��邩�E�D����Ă��邩�͊m�F����܂ł͖ϑz���������ǂ�������܂���ˁB
���Ɍ����A�N������D���ꂽ���nj�Q�ł��傤���B
����Ƃ��u�ߏ蔽���v���ȁB
�@�������A�T���d�������̂悤�ȋC���ɂȂ�����������܂��B
�ł��A�T�����������Ă邢��ƁA�����Ă��������l�̎���������̂ŁA�u�Ӎ߂��悤�v�Ƃ܂ł͎v���܂���ł����B
�@��̓I�Ɂw������Ƃ����ԓx�x�Ƃ͉��ł����H
�w���l�x�Ƃ́A�ߏ��̕��ł����H���Ƒ��E���e�����܂݂܂����H�@�������ł������ł��傤���H
�w���X�x�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȓ���̎��ł����H
���X�́A�����ɂ͏o���Ȃ���������܂��A���������ڂ��������Ă�������Ȃ��ł��傤���B
 �݂���
�݂���  2011/09/07(Wed) 13:36 No.247
2011/09/07(Wed) 13:36 No.247
���v�ł���B�����ϑz�A�����L��܂���I
���Ԃ�A���݁A���_�I�ɗ�������
�����邩�H�Ɛ����������܂��B
��ɗ����Ă��鎄�́A���F�A�����Ă���ƁB
�܂��A�ڐG������e�̐l�Ԃ����Ȃ����̂�
�ʂɂ������E�E�E�ƁB������Ă��܂��B
����ɁA�D�������́A
�����܂ł����葤�̔��f��ł��̂�
�ǂ��v���悤������ɂ��Ă���`��
�J�������Ă��܂��B
���́A�Ƒ��Ɍ����܂����Ă���̂�
�����̕���������܂��E�E�i��j
 ������
������ 2011/06/30(Thu) 17:53 No.233
2011/06/30(Thu) 17:53 No.233
���~�N�^�[�������F�����ƕ����܂����B
�������̖�ɂ��Ēm���Ă��邱�Ƃ́A
�P�A�o�ɐ���Q�̟T�Ɍ����Ƃ�������
�Q�A����p�ŃX�e�B�[�u���E�W�����\���nj�Q���N���邩���Ƃ�������
�̂Q�_�����ł��B
���͟T���C���̑o�ɐ���Q���Ǝ����ł͊����Ă���̂ŁA���~�N�^�[�������Ă݂����ȁE�E�Ǝv���܂��B
�ł��A���͔畆���ア�̂ŁA����p�ŁA�畆�Ȃ܂Œʂ����ƂɂȂ�����A���ʂāA���̖�ł�����ɑ��Č��ȃC���[�W�������ƂɂȂ邩������܂���B
�̂́A���a�Ɛf�f���ꂽ���A��Ɋւ��ẮA�����������܂����B
�����ǁA�o�ɐ���Q�Ɛf�f����āA��������Ȃ��A�����A���̂�ł�������E�E�Ǝv���A��̒m�����d����邱�Ƃ����߂Ă��܂��A���̎�������܂��B
����͎厡��܂����B
���[�}�X�Ŏ肪�k���悤�ƁA�厡��̂����Ƃ���䖝�B
�ނ��ނ������������Ƃ��܂�B
�ʉ@�͌��P��B
�ǂ�ȓK���Ȏ厡��ł��ǂ�Ɨ����I�������Ă����B�Ƃ����X�^���X�B
���~�N�^�[���ɋ����������āA�����A����ς�A�����ƈ���ł����ׂ�p���������āA�i��ł���a�@�ɂ������Ă����悩�����ƁA���Ȃ��Ă��܂��B
�����Ȃ�܂������A
���~�N�^�[���ɂ��āA�݂Ȃ���́A�ǂ̂悤�ȗ�����Ƃ��Ă����܂����H
 �V��
�V��  2011/07/06(Wed) 21:22 No.234
2011/07/06(Wed) 21:22 No.234
�����������C���ł��B
�����́A���{�g���[���ƃf�p�X�B
���[�}�X�͌��ʂ������Ȃ��̂ŁA�����ƟT���ɂ͈��܂Ȃ����Ƃɂ��܂����B
���[�}�X�̕���p�̕|��������܂��B
�T���̓A���L�T���ł��B
���~�N�^�[���͕���p���Ȃ���Έ���ł݂����ł��B
azami����ɏڂ����A�����Ă݂���̂������Ǝv���܂��B
�畆���ア�Ƃ̎��B
���́A�S�O���߂��ď��߂āA�X�e���C�h�i�}�C�U�[�N���[���@���t�玿�z�������j�̓h����h��A����͂悭�����ƁA���̐��N�͕p�ɂɓh���Ă��܂����B
�畆�����悭����̂ł����A�܂��X�ɍ����Ȃ��čĔ�����̌J��Ԃ��ŁA�����ڂ��キ�Ȃ�܂����B
�X�e���C�h�̕���p�̃��o���h�ƂQ�����O���炢�ɒm��܂����B
���A�E�X�e���C�h�����Ă��āA�����Â悭�Ȃ��Ă��܂��B
���_���猾���ƁA��X�e���C�h�Ǝ��R�����Ŏ��Ԃ��������Ă�����Ȃ�A�X�e���C�h�͎g��Ȃ��ق��������Ƃ������Ƃł��B
�����N�͎G�k�f���ɓ\���Ƃ��܂��B
 ������
������  2011/07/06(Wed) 22:52 No.235
2011/07/06(Wed) 22:52 No.235
azami����̃u���O�������q�����Ă��܂����B
�Ȃ��A�ƂĂ��A���x�Ȃ��b������Ă���悤�ŁA�������ł��ˁB
���~�N�^�[���̎��̃g���`���J���Ȏ���ɂ������Ē�����̂��A�s���ł��B
������A���͂قƂ�Ǘ������Ă��炸�A�����炵�����炢�����A�킩��Ȃ����̂ŁE�E�E�B
���́A���A�X�e���C�h���g���Ă��܂��B
��́A�z���X�e���C�h�ŁA�b���p�ł��B
�����ЂƂ́A���̌ۖ��̎�O�ɂł��鎼�]���J��Ԃ��Ă��āA���@�Ȃł���������Ă��܂��B
YOU TUBE���q�������Ă��������܂����B
 �肩
�肩  2011/08/06(Sat) 12:26 No.236
2011/08/06(Sat) 12:26 No.236
���~�N�^�[���̕���p�ł���X�e�B�[�u���X�W�����\���nj�Q�͍ŏd�ǂ̖�]�ł���A��ʂ̃X�e���C�h��_�H���Ȃ��Ǝ��S���܂��B
�X�e���C�h�́A�����A���ˍނŎg�p����̂ƊO�p��ł͑̓��Ɏ�荞�܂��ʂ����Ȃ�Ⴂ�܂��B
�܂��A�X�e���C�h�O�p��Ɋւ��Ă͋����̃����N�ƓK�Ȏg�p�ʁA�g�p���Ԃ����邽�߁A�K�Ȏ����ɓK�ȃ����N�̃X�e���C�h�O�p���h�z����A����p�͖w�ǂ�����܂���B
���~�N�^�[���̓X�e�B�[�u���X�W�����\���nj�Q���U�`�V%�̊m���ŕ���p����������悤�ł��A���̕���p���ł����_�œ����͒��~�A���܂֕ύX�ł��B
 ���~
���~  2011/09/08(Thu) 08:43 No.248
2011/09/08(Thu) 08:43 No.248
���ʂ��������Ԃ��݂Ď�����Ă݂�Ƃ����������܂��B
�Q�l�ɂȂ�Ȃ����킩��܂��̌��҂Ƃ���
 ������
������  2011/09/15(Thu) 17:55 No.269
2011/09/15(Thu) 17:55 No.269
���������ݎn�߂܂����B���̓f�p�P��������ł���̂ŁA�厡�オ�T�d�ɍs���Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����āA�Ƃ肠�����A�Q�T�~�����u�����^���Q�T�ԑ����܂��B�厡��̌v�Z�ł͈ێ��ʂɂ���܂łɂR�J��������炵���ł��B
���A�T�����������Ђǂ��̂ŁA������Ƃ�������������ł����A�]�@���ĂQ�J�����炢�o���̎厡��́A��A�R�T�܂͏o���Ȃ��Ƃ����Ă���̂ŁA�ς��邵���d������܂���B
�Ƃ肠�����́A����p���łȂ����Ƃ��F��݂̂ł��B
���A
 ������
������  2012/11/12(Mon) 20:09 No.739
2012/11/12(Mon) 20:09 No.739
�ς݂܂���A�f�������̂ł����A�ނ��ނ����nj�Q �̓��[�}�X�̕���p�ŏo���̂ł��傤���H
 �肳
�肳 2011/06/27(Mon) 17:31 No.228
2011/06/27(Mon) 17:31 No.228
�͂��[�E�E�E
�G�k�f���ɂ������܂������A���͍��A�O�N�Ԃ�ɑ�w�ɖ߂�葱�������Ă��܂��B
���ꂪ�A������A���̑�̓���ł���Tomio Koyama�Ƃ������p�قŁA�A���o�C�g��W�����Ă���̂ɋC�Â��A�����ɗ������𑗂�܂����B�O�����Ј��̕�W�����Ă��āA�����������āA���̎��͗�������������ǁA����͑呲�Ƃ��̏������S�R�Ȃ��āA�B��̏������u���邭���C�ȕ��v�Ȃ��́B
�E�E�E���������ꂪ�A�悭�悭�ڍׂ����Ă݂�Ɓu�T�ܓ����v�u�P�P���`�P�X���v�̎d���ŁA����ł͎��ԓI�ɑ�w�Ɨ����ł��Ȃ����Ƃ������B
�ǂ������I�ׂȂ��Ƃ��߂Ȃ̂��Ȃ��E�E�E�܂��A�܂��̗p����Ă���l���悤�A�Ǝv���Ă�����A
����l����̗c����̗F�B���������Ɖ���āA���������M�r�������Ă��܂����i�܁j
�����N���a�̐l�Ɗւ��O�͂Ђǂ��Ђ�������ŁA�l�ԊW���Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂��Y�݂̎킾�������ǁA
�����̂��铯�a�҂Ƃ̊ւ��ƊW���������Ƃ��킩���āA���Ⴀ�����䂤�ւ�荇�������Ă閈�����A�u����ҁv�Ƃ̊W�A�Љ�Q����ۂĂ邱�ƂɂȂ��邩�Ȃ��A�Ɗ��҂��Ă�������ǁE�E�E
����v�X�Ɂu����ҁv�i�ƌ����Ă��Ƒ��̂悤�ɓ���݂̂���F�B�����j�Ɖ���āA�قƂ�lj�b�����藧���Ȃ��āE�E�E�B
���w�A���Z�̂��납��p�ɂɉ���Ă������o�[�Ȃ̂ɁA���̕a�C�����ǂ��Ă���A���̂悤�ȓ�����Ɏl��قǍs���āA�l��S���̒�������āA���ނ��āE�E�E
�������O����Ȃ�������ł��i���j�܂��A�Ō�܂ł���ꂽ����ǁA
���͐l�Ɖ�Ɓu�A�p�V�[�Ǐ�v���N�����Ă��܂��̂���Łi�A�p�V�[�Ǐ�Ƃ́A���̔߂����Ƃ�����āA����\���A���ȕ\�����̂ł��ɂ����Ȃ��Ă��܂��B������A������Ƃɂ��ɂ����Ă����ɍ����Ă邾���ŁA���t���قƂ�ǔ������Ȃ����A�������l���Ă邱�Ƃ���肭�`���Ȃ��B�j�����䂤�Ǐ��Ă铯�a�҂̕��A�ق��ɂ�����̂��ȁH��������ł́u�l�`�a�v�Ƃ��Ă�Ă��邯�ǁE�E�E�i��j
�Ƃɂ����A���a�҂Ɗւ�閈�����߂����Đl�ԊW�ɏ������M�����Ăė����̂ɁA����œ����ɃA���o�C�g�Ƒ�w�ɂ܂Ő\�����̂ɁA
����́A���M�r���ł����E�E�E�i�|�|�G�j�\���͂������ǁA�ق�ƂɁA����҂̒��ł����Ƃ���Ă���̂��Ȃ��B
����ҁE�����҂��ċ敪�������邱�Ǝ��̂��܂�D�܂����Ɗ����Ȃ��l������Ǝv������ǁA���ɂƂ��Ă͎v�z�I�ȉ��l�ςƂ��̂���ʂ�ȑO�ɁA�����̋ꂢ�����ŁE�E�E���̋敪���́B
Tomio Koyama�͖{���ɖ��̂悤�Ȃ��d�������ǁA���s���Ă������ȊO���܂���f�̂�����Ȃ���w��w���Ƀ`�������W�I�̕����A�Ó����Ȃ��E�E�E�ł��ATomio Koyama���患�i���j�F����s�m�����ɍs���邱�ƂƓ������炢�������I�����́i��j
���[�E�E�E�B���̐l�����܂ł����Ƃ̔Y�݂ł����ǁA�ŋߋ����Ɋ������̂ŁA�����ɒԂ��Ă݂܂����B����ҁE���邢�͕a�C�ɂ��܂藝�������ĂȂ��l�X�E���ł͎������Ȃ��Ȃ��@�\�ł��Ȃ����āA
�����Y�݂������Ă��������̂��Ȃ��B
�]�肳
 �V��
�V��  2011/06/28(Tue) 22:19 No.229
2011/06/28(Tue) 22:19 No.229
�l���Ⴂ���A�s����Q�ŁA�ُ�ɋْ����āA�����͂��ȉ�b�����Ă��܂����B
�����݂ł����A�ΐl�o�����R�ςގ��B
�A�p�V�[�̂悤�Ȑ_�o�ǎ҂̓����Ƃ��āA���ӎ��ߏ�ɂȂ�A�������ɂȂ�C���Ȃ̂ŁA�ӎ��I�ɑ�������肰�Ȃ��ώ@���āA�O�����ɂ��邱�ƁB
��������A����̖{���≉�Z��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
����̋C������������������Ƒΐl�s���ł������Ȃ��Ȃ�����A�����ɂǂ̂悤�ɔ������ĉ�b�����炢�����A�u���ɂł���悤�ɂȂ�܂��B
���q���m�̉�b�͒j�q���m���C���g���Ă��܂��ˁB
�肳����̕��͕\���\�͍͂����ł���B
����̊�̕\��Ɛ��Ƒԓx�ŋC�������@��������ł��B
�����̋C���������Ăق����͑���̏���Ȃ̂ŁA�قǂقǂɂ����ق��������Ǝv���܂��B
�����̋C�����̑S����`����͖̂����Ȃ̂ŁA�T�����炢�`���Ώ�o�����炢�̐S�\���ł����Ǝv���܂��B
 ����
����  2011/06/29(Wed) 04:58 No.230
2011/06/29(Wed) 04:58 No.230
>
���͐l�Ɖ�Ɓu�A�p�V�[�Ǐ�v���N�����Ă��܂��̂����
>
�@�@�@����ŁA����܂ł̂肳����̓��e���ʕ��͕\���͂Ǝ��ۑΖʂ����Ƃ��̉�b�Ƃ̎��̈�ۈႢ�̗��R���������C�����܂��B
�@�@�X�e���I�^�C�v�I���z�ł́A���{�����̓����Ƃ��āu�����ѕ����v�u���l�����Ď��ȕ\���v������܂��B�����A���Ăł́u���҂͈Ⴄ�����������Ă���v�u�����瓢�_�i�f�B�x�[�g�j�E��b���ė������悤�Ƃ���v����������܂��B
�@�@�����́A�A���q���ł肳����́A�n�[�t�ł���܂łɊw�Z�Ŕ|���Ă�����b�E�l�Ƃ̐ڂ������A���{�Љ�ł͕s�K���Ɩ��ӎ��Ɋ����Ă��āA���ꂪ���̏Ǐ��ǂ��Ă��錴���̈�ʂ�����̂ł́H�ƁA��҂ł��Ȃ��̂Ɏv���܂����B
�@�ƁA�����̂������悤�ȏǏA���ɂ��ߋ��Q�x�̋A�����ɂ���������ł��B���݂́A����Ӗ����́u�ςȂ�������v�ƁA�J�������Ď��ȕ\���E���҂Ɛڂ��Ă܂��B�����ɑ��҂Ɠ���������A���ʓ_�����o���Ă��������b������Ƃ����X�^���X���Ƃ��Ă܂���B
�@�@�������́A���������ł������V�������������悤�Ɂw�ꐔ�x�w�ꊵ��x���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�����A�����̕��w��i�⏑�ЁA�G���L���ȂNJ����Ǐ�����̂�
�L�������m��܂���B
�@�@�@�����炸�A������߂��A�p������Ă��������B
�@�@���E�Ɋւ��ẮA�������g���C���ꂽ��Ǝv���܂��B�g���C�����Ɍ��������A�g���C���Č����������A�������牽���l�����w�ԋC�����܂��B��L�́w�ꊵ��x�ɒʂ�����̂�����Ǝv���܂��B�i�]�v�Ȃ��������������j
�`�����X�́A�����ȂƁA�v���܂��B�i�����̔O���߂āj
�@�@�ł͂܂�
 �肳
�肳  2011/06/29(Wed) 09:44 No.232
2011/06/29(Wed) 09:44 No.232
���J�Ȃ��Ԏ��A���肪�Ƃ��������܂��B������Ƒ̒���������ĂȂ��̂ŁA�ꉞ�̒Z�����Ԏ��ɂȂ�܂��B
���[��A�܂����̏Ǐ�ł���u�A�p�V�[�v�ɂ��Ď��̐����s���������C�����܂��B���邢�́A�����̏Ǐ����ʓI�ȁu�A�p�V�[�Ǐ�v�ƕ\������̂��A��������Ă���̂������ꂹ��B
�A�p�V�[�i�Ƃ��������̏Ǐ�́j�A�V�����q�ׂ�ꂽ�悤�ȁA�ΐl���|���邢�͕s���E���N����A�������q�ׂ��悤�ȃJ���`���[�V���b�N�Ƃ͐������Ⴄ�Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɂ�������Ɖ�������Ɏ����A�p�V�[�Ǐ�ɂȂ������Ƃ́A�Ȃ��ł���[�i�j�Ȃ��̋�C�ǂ�łȂ��o�J���邢�����A����͍��Ж�킸���̒n�̐��i�ł��i�O�O�G�j
�{���̎����̋C������l�������̕ω���l�ԊW�Ŏ��ہi�s����J���`���[�V���b�N�Ƃ����`�Łj�ς��A�Ƃ�����肩�́A�{���̎������ς��Ȃ��̂�
�Ȃ������̖{���̎����������o���Ȃ��B�u�l�����킢�v�Ȃǂ̎v�z�A�s���E���N���Ȃǂ̊���̕��Q����ɗ���Ƃ�����肩�́A�܂��{�����̐l�����Ƃ���̂͂܂��������R�Ȃ��Ƃ����A���������Ă���̂ɁA�i���Ȃ݂ɂ��̓�����ɗ����̂͒j�������������A�p������{����b���鎄�Ɠ����n�[�t�ł������A��������݂̂���F�B�ł����j
���́u���R�A���S�v�Ȏv�z�⊴���\������͂��Ȃ��Ȃ����Ⴄ�A���Ċ����ł��E�E�E�B�܂�u����v�̎x��łȂ��u����\���v�̎x��ł��ˁB
�ł��m���Ɍ��ʓI�ɓI�Ǐ�Ƃ��āA�l�Ɖ���Ƃɑ��ĕs���ɂȂ�����A���E����������悤�ɂȂ�̂ŁA�������������ɂ́A
�V������₾���������悤�ɁA�`�������W�݂̂��Ǝv���܂��B�{��ł́u����v�����邽�߂ɂ��A�N�T�a�҂̊ԂŃ��n�r���I�Ɂu�l���v����̂��������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B
�M�d�ȃA�h�o�C�X�A���肪�Ƃ��������܂��B��݂ɂȂ�܂��B
���Ȃ݂ɁA�V������Ƃ�������́u�A�p�V�[�v�̒�`�Ƃ́A�ǂ��䂤���̂ł��傤���H���͑O���玩���̏Ǐ��������鎞�A���̌��t�𐳂��������ĂȂ��̂ł́E�E�E�Ɗ����Ă��̂ŁA�ق��̐l�̍l���ɋ���������܂��B
�p��̒���ł́u������v�Ƃ��������ł����A���̒��ł͂�͂�u����\���̏o���������܁v�Ƃ��������ł��傤���B
���Ȃ݂ɁA���͂悭�A���͏�̎��Ǝ��ۉ�����������Ⴄ�A�ƌ����܂����A����݂͂�Ȃ��������v���܂����u�O�̎����v�u���̎����v�̈Ⴂ���Ǝv���܂��B���i�ɗ��\��������Ă����킯���Ⴀ��܂��A�i�j����ς蕶�ʂ��Ɛl�ɂ��܂茩���Ȃ����ʓI�Ȏ������o����Ƃ����ʂ�����Ǝv���܂��B������V���������悤�ɁA���̂悤�ȓ��ʓI�ȁA�f�B�[�v�ȗ������J�W���A���ȃR�~���j�P�[�V�����ł���Ԃ���ԋ��߂�͍̂T���������������Ȃ��A�Ƃ��v���܂����B
����ƂȂ��āA��������̃A�����J�E���{�̃R�~���j�P�[�V�����ɂ������Ă̑�����A�����[���ł��ˁB���{�l�͎Ќ�I�ȏ�ł́u��яo���B�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���A�Ƃ������������邩������܂��A���̕��X�̓��ʐ��E�͏[�����Ă���C�����܂��B�A�����J�ł́u��individuality�v���Ќ�I�ȏ�ł��]������܂����A�����Ӗ����Ȃ��V���b�L���O�E�p���t���Ȃ��Ƃ�������A�u���������߂̌��v�݂����Ȋ����ŁA���{�́u��߂�ꂽ���v�قǁA�l�I�ɂ͐^�������������܂���B
����A�ȂZ�������Ƃ������Ă����Ԃ�E�����Ȃ��璷�������Ă��܂��܂����i�O�O�G�j���_��Q�Ɛl�ԊW�A�ǂ����R�Ȍ`�ŗ��������Ă������A�傫���ۑ�ł��ˁB���̂Ƃ���V������Ƃ������A�h�o�C�X���Ă����������悤�ɁA�Ƃɂ������H���Ă݃}�X�B
�]�肳
 �肳
�肳 2011/06/17(Fri) 19:13 No.225
2011/06/17(Fri) 19:13 No.225
��ӂ��ȁA���{�b�g�ɂ��Ă̓��W���e���r�ł���Ă����B
�����\���郍�{�b�g���Č����̂����āA�s�v�c�Ƃ����ɐڐG����l�͊���ړ�������̂��\�炵���B
���{�b�g�����҂ɂ͓�^�C�v�����āu���{�b�g�͂����܂Ől�Ԃ̂��߂ɖ𗧂c�[���̂悤�Ȃ��́v�Ǝv���l�Ɓu���{�b�g���A�O���I�ɂ�����I�ɂ��A����Ɛl�Ԃɋ߂Â��Ă��f�������邾�낤�v�Ǝv���l�B
��l�̐l�Ȃ�āA�u�������{�b�g���l�������Ă�悤�ɂȂ邾�낤�v�Ƃ܂Ō����Ă���B
���{�b�g����������Ƃ��āA��̂����Ȃ���̂ɂȂ邾�낤�H
�Ƃ����Ƃ܂��A���ۊ�������͕̂s�\�Ƃ��Ă��A�ڐG����l�Ԃ����{�b�g���������������l�Ԃ��̂悤�Ɏv���Ă��܂��قNJ���ړ����Ă��܂��A�Ƃ����Ӗ��ŁB���́u���{�b�g�l���錾�̌����ҁv�͂����
�u�܂胍�{�b�g���h�l�ԂɂȂ�h����������A���̃��{�b�g��l�Ԃ������ł��Ȃ��Ȃ��������낤�B�Ƃ��͖𗧂��A�𗧂��Ȃ��Ȃ����珈������̂�������O�����A�l�Ԃ͖��ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă��A�����鉿�l�̂���l�Ԃł���A�Ȃ��Ȃ��r���ł��Ȃ����̂ł͂Ȃ����B�v
�Ǝ��̉��߂��܂߂Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă����B
�l�Ԃ̂悤�Ȋ���������{�b�g�́A�܂�u�����Ȋ���v�����̂��낤���B�悭�r�e�Ƃ��Ń��{�b�g�͐l�Ԃ������ɂȂ��Ă��܂����A�s���R�Ȍ`�A�Ɣᔻ���Ă���悤�����A
�����Q�������Ƃ��ẮA�u�����Ȋ���v�ɂ��ĂƂĂ��s�v�c�Ɏv�����A�Y�݂̎�ł���B
�K�^�J�Ƃ����f���A���j�Y�Q�O�R�O�Ƃ�������ł��A���{�b�g�ł͂Ȃ����A�l�Ԃ̂c�m�`�����ǂ��u�����Ȑl�ԁv����邱�Ƃɐ��������ߖ�����`���Ă���B�����̍�i�Ƃ��A���́u�����v���ւ̔ᔻ���܂߂Ă���B
�t���C�g��J���̂悤�Ȑ��_���͎҂́A���̐��̉Ȋw�ƈ���āA�l�Ԃ̊���E���_�����́u��v�ɕ�܂�Ă��āA�𖾂�����Ȃ��ʂ�����A�ƌ����Ă���B
�����Q��S���������ɂƂ��āA����̎����Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��Ӗ�����̂��낤�B���߂Ď��ɂƂ��āu�����v���i���ꂪ�ǂ̂悤�Ȃ��̂����A�悭������Ȃ�����ǁj�Ƃ͈Ⴄ���̂ȋC������B
�������́A���̐��_�́u��v�A�i��Ԑ��̂̒��Ől�ԓI�ȖʁH�j�ɂ悭���������G��Ă���C������B���ꂪ�l�Ԃ̐S�����𖾂���ɂ������ďd�v�Ȃ��Ƃł�����C������B
�����قǂ̌����҂��u�l�͐l�Ԃ���藝�����邽�߂ɁA���l�Ԃɋ߂����{�b�g�̐���ɓw�߂Ă���v�ƌ����Ă����B
�������A���{�b�g�Ɂu���ӎ��v�u�؍݈ӎ��v�u��v�͎��Ă�̂��낤���B�����݂̐l�X�́A�������̂悤�ȐS����ԂɊ���ړ��ł��Ȃ��i�K�ɂ��邯�ǁA���̂悤�ȐS����Ԃ����{�b�g�ōČ��ł���̂��낤���B
���̃e���r�ɏo�Ă����{�b�g�́A�ƂĂ����A���ɑ��ʓI�ȁu�\��v�������Ă��A����ǁA
����͊O�ς́u�\��v�����ł͂Ȃ��A���̗��ɉB���ꂽ�A�u�S�v�̕\��ł��邱�ƁA����͐��g�̐l�Ԃɂ������ĂȂ��ł��낤���Ƃ��A
�Ȃ�ƂȂ��l���Ă��鎩���ł����i�O�O�j
�ł����{�b�g�Ȋw�́A�Ȃ����ƂĂ��������낢���I���̎����̒��ł��C�����̖����ŁA���Y�ݒ��ł��i�O�O�G�j
�u���{�b�g�͂����l�������Ă邾�낤�v�Ƃ��������ǁA�N���a�҂͎��ێЉ�ɔF�߂��ĂȂ��ʂ����邩��A�Ȃ��G�ȋC�����E�E�E�B
�|�肳
 �肳
�肳 2011/06/15(Wed) 23:42 No.224
2011/06/15(Wed) 23:42 No.224
�����A���a�҂̒��ԂƂԂ��荇���āA�N�T�a�҂̊W�̖����ɂ��āA�l���Ă��B
�������O��Ƃ��āA���������̏Ǐ�ɂ�����̋����◝�������Ă邯�ǁA �Ƃ��ɐe���W�ɂȂ��āA��������Ŋ�������悤�ɂȂ�ƁA����ɂ��X�g���X������鎞�����A���Ԃ��Ă��܂��B
���a�҂Ƃ��āA�����������ǂ��䂤�S���ɂ��āA���̏Ǐǂ�قǂ炢���A�ǂ�قǃR���g���[���ł��Ȃ����A�[���������Ă�̂ɁA�Ɋ����Ă�̂ɁA
����ɂ��A�����ɒ��q�������Ȃ��Ă��܂��ƁA�����瓪�ŗ������Ă��Ă��A���q�������Ă��̗��������s�Ɉڂ��S�̗]�T�����ĂȂ��B�܂�A����̋C�������~�߂āA�u���v?�v�Ƃ₳���������������Ȃ��قǁA�������g�̐��_��Ԃ��x����̂Ő���t�B
�t�Ɏ������g������ɋC�������~�߂Ă��炢��������ɂ��āA �������������������̏Ǐ���~�߂�ꂸ�ɂ���ƁA �u���Ŏ~�߂Ă���Ȃ���?�v�u���a�҂Ƃ��āA�������Ă���Ă����͂��Ȃ̂ɁE�E�E�v�ƏǏ�̈����ɂȂ���A���z�ɂȂ�����E�E�E�B
�����l����ɂ́A�N���a�̈�Ԃ̔Y�݂́u�Ǘ��v�Ɓu����̖������v���Ǝv�����ǁA
�ł�����Ɠ�Ƃ��̔Y�݂��ɉ������Ă����u���a�҂Ƃ̊W�v���ǂ�ǂ�e���Ȃ�ƁA��L�̂悤�Ȗ�����������B
���́A�N���a�҂Ƃ����W�܂肪�A���e���◝����l�ԊW�ɂ��ĐV���ȁA�L���ϓ_���Љ�ɖ�����f��������ƐM���Ă�B �ł��A���̑f�������邽�߂ɂ́A�����Řb�����������z��������Ȃ��B�ǂ�����Ă�����������̂��E�E�E
����ς�A��ԂЂǂ��Ǐ�̂Ԃ��荇�����܂߂āA����̂܂܂̎����������������Ɏ~�߂����A��������Ƃ���n�܂�̂��Ȃ��B���ۍ������̐l�ƒ����肵�����A�Ȃ��傫���R�����z�����悤�ȁA�J�������Ɛ[�܂����C�������ς������B
�����̂悤�ȗ���ɂ���l�́A���̒��ł͏�Ɏ������p���ɂ��邯�ǁA����ς�C�����I�ɂ͎����̂��ƂŐ���t�ɂȂ����Ⴄ���̕a�C�B����ȐS���ɂ���l���W�܂����J��[�߂�ꂽ��A�t�ɂ������p���[�Ƌ��e�͂ݏo�����Ƃ��o�����Ȃ�����!����ȋC������B
�������݂̍������A�������������{�S�̋����Љ�w�ׂ邱�Ƃ������ς�����Ȃ��Ǝv����ƁA ���e�����a�҂ƁA�����ƂȂ����[�߂Ă��������Ǝv���Ă���B
�Ԃ��荇���͐l���݈ȏ�ɑ�ς��������ǁA�l���݈ȏ���J����邽�߂ɁA�N���a�҂Ƃ̊W�́A�w�͂��Ă��������B
-�肳
 �肳
�肳 2011/06/13(Mon) 16:23 No.223
2011/06/13(Mon) 16:23 No.223
���͍���Q�҃X�|�[�c�Z���^�[�Ƃ����{�݂𗘗p���Ă������ǁA
�g�̏�Q�҂����_��Q�҂��A������āA
���܂�b�����@��̂Ȃ��g�̏�Q�҂̕��Ƃ��b�����Ă���ƁA
�����u��Q�v�ƌĂ�Ă��Ă������̈Ⴄ����l�������Ƃ��Ȃ������ړ_�Ƃ������āA����ɂ��ċ����������n�߂��B
�g�̏�Q�҂̕��Ƙb���Ďn�߂Ɋ��������Ƃ́A�����܂����������B��ʓI�ȍl������������Ȃ�����ǁA���̐l�͎�������Q��S���Ă��邱�Ƃɂ��ăV���b�N��Ђǂ��������݂������邾�낤���A���_���̂ɂ͎��̂悤�Ɂu�x��v���������ĂȂ��킯������A���̟T��ԁE�g���E�}�E�R���v���b�N�X����R���z�����]�́A�������Ă���̂ȋC�������B
�ł����̏ꍇ�́A���_���̂Ɂu��Q�v������킯������A����Ɋւ��Ă̓I�ȃV���b�N�������z���悤�Ƃ��Ă��A���X����̂悤�ɁA��R�̎��̈�R�A�g�̎��ɂ�����g�̂悤�ɁA���z���甲���o���Ȃ��悤�ȋC������B
��������ʓI�Ȏ��̑���ۂŁA�����P�������ċ�ʂł��邱�Ƃł͂Ȃ��Ƃ͔F�����Ă��邯�ǁA
�m���ɐ��_��Q�Ɛg�̏�Q�ɂ͎��o���ׂ��ړ_��A�����[���Ⴂ�Ȃǂ�����Ǝv���B����܂�l�������ƂȂ�������A�Ȃ��l���n�߂��狻���[�������B
�Ⴆ�A���_��Q�́u�����Ȃ��v�a�C�ƌĂ�Ă��āA���ꂪ�f�����b�g�̂悤�ɂ������͊����Ă������ǁA�u������v�a�C�ł���g�̏�Q�҂̔Y�݂�炳�A��̕a�C�̐����̑���́A�����Ȃ���̂Ȃ̂��낤�B���͖{���������ƁA���������ɁA�Ƃ��������o�I�ɁA�u������v�a�C��S�����Ƃ��ƂĂ��|���B���̕|���̍���Ȃǂ����Ȃ̂����A�l���Ă݂����B
�u�Y�݁v�ł͂Ȃ�����ǁA�݂�Ȃōl���Ă��������Ȃ��Ǝv�������ƂȂ̂ŁA�����ɍڂ��Ă����܂��B
�i���͑O�����N���a�̈�ԓ����I�ȓI�Ǐu����̖������v��u�Ǘ��v���Ǝv���Ă����B�����䂤�Ӗ��ŁA�g�̏�Q�҂������Ȃ̂�������Ȃ��ȁA�傫���ړ_�ƂȂ邩������Ȃ��A�Ǝv�����B
�i�u�j�����N�T�a�҂��Љ�ɗ������ꂸ�A���������ɐ[�������ƈ����������v�Ȃ�Ă�����������������f�G���Ȃ����čl�������Ƃ��邯�ǁA
���_��Q�҂Ɛg�̏�Q�̃��u�X�g�[���[���A���܂łȂ����̂ŁA���̈���̍�����l�̂Ȃ��肪�ǂ����炭��̂��A�l����Ƃ������낢�i�O�O�ւցj
�|�肳
 �Ȃ�
�Ȃ�  2011/06/22(Wed) 23:15 No.226
2011/06/22(Wed) 23:15 No.226
��������b��ł��̂Ń��X�����Ă��������܂��B
���Ȃ݂Ɏ����̂��Ƃ�b���Ă����܂��ƁA
���͕Њ���������u�g�̏�Q�ҁv�ł���i�������`������Ă���̂ŁA�����b���Ă��Ȃ��l�ɂ͂킩��Ȃ��悤�ł��j�A
�����N�T�a�i���Ԃ�U�^�j�Ɛf�f����Ă��܂����B
�u���āv�Ƃ����̂́A�ߋ��̕��E���̒��q�̕ω�����厡����N�T�a�ł��邱�Ƃ��^���A���̌�u�K����Q�v�ɐf�f�����ς��܂����B
�����Ƃ��ẮA�u�N�T�a�v����{�Ɏc���Ă���A���̏�Ɂu�K����Q�v������ƌ��Ă��܂��B
���݂ł̓����^���n�̖�͂��܂Ɉ��ސ�����������āA�C���������R����E�R���_�a����S������ł��܂���B
�ȏオ���̎���ł��̂ŁA�����O���ɒu���Ă���������Ǝv���܂��B
�肳����̏����ꂽ���e��ǂ�ł��܂��ƁA�ǂ����l���Ă����邱�Ƃ����̒��́u�C���[�W�v�ɕ��Ă�����悤�Ɋ����܂��B
�g�̏�Q�҂ɂ���A���_��Q�҂ɂ���A�l���Ȃ�������Ȃ��̂́A�ǂ�����u�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ƁB
�]���āA���������łǂ������x�Ⴊ����A�ǂ̂悤�ɂ��Ă����ɑΏ����Ă������A�Ƃ������Ƃ��l���Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂��B
���̊ϓ_���猩��ƁA���_��Q�ҁA�����N�T�a�҂̏ꍇ�A�g�̓I�@�\�ɂ͎x�Ⴊ�Ȃ��̂ŁA�C���������ɖ߂�Ό��N�l�i���Ɍ������ʁj�̐������\�ł��B
�ł��g�̏�Q�҂̏ꍇ�A�ǂ̂悤�ɂ��Ă����ʂ̐����͖����ł��B
���̏ꍇ�A�Њ�������Ă���Ƃ������Ƃ́A���͂���Ԃ������܂���B
�i���ɕЊ�Ō��ɖ߂邱�Ƃ͂���܂���B
���ł͕Њ�ł�������x���̊�������A����قǎx��͂���܂��A�͂��߂̐��N�Ԃ͍s�i�ł��ӂ�ӂ炵�Ă�����Ǝx�Ⴊ����܂����B
����Ǝ��͋��x�̋ߎ��ɗ������������Ă��܂����A������c�����ڂɕ��S�������������̂ł���Ǝv���Ă��܂��B
���̂��Ƃ��l�����
>���̟T��ԁE�g���E�}�E�R���v���b�N�X����R���z�����]�́A�������Ă���̂ȋC�������B
�Ə�����Ă��邱�Ƃ́A�����̏�Q����ԋꂵ���ƌ����A���̏�Q�Ɋւ���z���͂◝�����܂��܂����ȂƊ����܂����B
�C���̃R���g���[�������ł���Ό��N�l�Ƃ���قLj��Ȃ��������ł����N�T�a�҂ƁA���͂⎸�������͎̂��Ԃ��Ȃ��g�̏�Q�A���̈Ⴂ�͂ǂ��v���܂����H
>���͖{���������ƁA���������ɁA�Ƃ��������o�I�ɁA�u������v�a�C��S�����Ƃ��ƂĂ��|���B
�����z������ɁA����͂��������o������ĂȂ����̂̋��|�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������o�����Ă���A���ł����ꂴ��܂���B
���̊J�����肪�ł��܂��B
�����Ƃ����̏ꍇ�́A�Њ�Ƃ����Ă��������͂�1.0���炢����^�]�Ƌ��������Ă���̂ŁA��Q�Ҏ蒠�͎��Ȃ��悤�ł��B
���_��Q�ɂ��Ă��A�Q�����ȏチ���^���Ȗ�����܂Ȃ��Ă��悢��Ԃ������Ă���i�����Ƃ����N���S�����������܂Ȃ���Ԃ���������łނ����T�ɗ������݁A�����ꂵ�݂܂������N�g�̍��͂���A�T�̏�Ԃł����j�A���C�ȏ�ԂȂ̂ŁA���ꂵ��ł�����肳����ɑ��郌�X�Ƃ��Ă͕s�K�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��邩������܂���B
>�j�����N�T�a�҂��Љ�ɗ������ꂸ�A���������ɐ[�������ƈ����������v�Ȃ�Ă�����������������f�G���Ȃ����čl�������Ƃ��邯�ǁA
>���_��Q�҂Ɛg�̏�Q�̃��u�X�g�[���[���A���܂łȂ����̂ŁA���̈���̍�����l�̂Ȃ��肪�ǂ����炭��̂��A�l����Ƃ������낢�i�O�O�ւցj
�u��Q�҂�����҂��������Ă����Ȃ�������Ȃ��v�Ƃ������_��������ƁA��肢�������[�݂��o��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�s�K�ȓ_������Ύw�E���Ă���������Ǝv���܂��B
��낵�����肢���܂��B
 �肳
�肳  2011/06/23(Thu) 00:31 No.227
2011/06/23(Thu) 00:31 No.227
�Ǝ��͈ꉞ�������Ă������߂ɁA���̂悤�Ȓi����u���܂������A
�S�̓I�Ɏ��̏������݂��z���͂����������m�A�y�і��_�o�Ȃ��̂ƂȂ���������̂ł���A����͂��l�т��܂��B
�f���P�[�g�ȃg�s�b�N���Ƃ͔F��������ŁA���̑f���ȑ���ۂ�Ԃ낤�Ǝ��݂��̂ł����A����͂����������t��I��ŁA�ǂݎ���l���ď����悤�w�߂܂��B
���������̌����Ƃ��ẮA��͂�u�N���a���g�̏�Q�̕����h�����h���邢�́h�y�h�A�v���邢�͉����P���ȃC���[�W�ɊҌ����悤�Ƃ�������͂܂������Ȃ��A
�f���P�[�g�ȃg�s�b�N�Ȃ���A�݂�Ȃŗ����ɁA�I�[�v���ɍl���Ă����ׂ��ł��낤���Ƃ��Ǝv��������ł��B
�Ȃ�����͐g�̏�Q���u���Ԃ��̂��Ȃ��v�Ƃ������ɕ\�����A�N���a�́u�C���v��������E�E�E�ƕ\�����Ă��܂����A
������̑̂̏�Q���̂́A���Ԃ��̂��Ȃ����̂�������܂��A�ʂ����āu���_�v�̏C���́A���Ԃ������Ȃ��ƌ������̂ł��傤���B
���͂��̐e�L�����������ӁA���͐g�̏�Q�҂ŁA�ƂĂ��O�����ȁA�ƂĂ����_�I�ɐc�̋������Ƃ��F�B�ɂȂ��āA�ނ͕��ʂɌܓ����̉�Ђɒʂ��A�c�Ƃ����Ȃ��A�������i�ɐM������Ă���A�Ƃ̂��Ƃł����i�d���������邩��A����قǂ���A�Ƃ̂��Ƃŏj
���̏Ռ��I�ȏo��̏�ŁA��L�̎��́u����ہv��Ԃ���������ł��B��������g�̏�Q�҂ł��A�����ʂŌX�ɂ���đ傫�ȈႢ�����邱�Ƃ͔F�����Ă��܂��B
���͂Ȃ��������悤�ɁA���_��Q�҂Ɛg�̏�Q�҂́u�Ⴂ�v���A�ނ���u�ړ_�v�i�Ȃ�����̗�Ō����܂��ƁA�u�������Ȃ�������Ȃ��v���Ɠ��j�ɂ��ċ�������������Ă��܂��B
���̒��ŁA�Љ�I�ɐ��݂��Ă��܂����\�ʓI�ȁu�C���[�W�v�i���́u������v�a�C�ɂ��Ă̕|�ꓙ�j���f���ɕ������������Ƃ��ߒ��I�ȈӖ��ő厖���Ǝv���܂��B�ړ_�̂���l�X�̊Ԃɂ���\�ʓI�ȋ��E������芷���邽�߁A�Ƃ����_�ł́B
�������������ŁA�Ȃ�����́u�C��������E�E�E����l�̐������\�v�Ƃ����u�C���[�W�v�́A�����Ђ�������܂��B�����Ƃ��Ă͐������Ǝv���܂����A�N���a�͎�����u�����a�v�ł���A�Ⴆ�ΐg�̏�Q���u�̖̂����a�v�ƌĂԂƂ���A�N���a�́u���_�̖����a�v�ł���A
�u�ǂ��炪�����I�ɂ����ƗL�����v�Ȃǂɏd�_�����Ă��肩�́A���̕\�ʓI�ȈႢ�̗��́A�{���I�Ȑړ_�ɂ��ĒNj����Ă��������Ǝ��l�͊����Ă��܂��B
�Ⴆ�A�Ȃ����G��܂����u�K����Q�v�B����͌��t�������܂��ƁA�g�́A���邢�͐��_��Q�́u�I�Ǐ�v�ƌĂׂ�Ǝv���܂����A���͂���ɖ{���̕a�C�����ꂵ�ʂ�����܂��B��̓I�Ɍ����܂��ƁA�a�C�ɂ��u�I�ȂЂ��������ԁv�Ɋׂ�A���������藧���Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��B
�Ȃ����u���������Ȃ�������Ȃ��v�Ƃ����T�O��g�̂Ɛ��_��Q�̐ړ_�Ƃ��đ�����̂́A�ƂĂ������[�����Ƃ��Ǝv���܂��B������u�Љ�Q���v�ƌ��������܂��ƁA���́A���_���g�̏�Q���u�Љ��O�ꂽ�v����ɂ���ƐM���Ă���A�Љ�Q�����ł��Ȃ��A�Ƃ�����Q�����z���邱�Ƃ��{���I�Ȑl���̖ڕW�Ȃ̂��E�E�E���邢�́A�{���̎����̎��R�Ȍ`���t�ɎЉ�����ׂ����B�{���I�Ɂu���Ԃ��̂��Ȃ��v�v�f�ɂ��Љ��O��Ă���̂ł���A�����ȁu�Љ�Q���v�ȊO�̐����͖]�߂�̂��B
�ƂĂ������[���e�[�}�ł���Ȃ���A�ƂĂ��f���P�[�g�ȃe�[�}�Ȃ̂ŁA���Ƃ��Ă͒����I�ȗ��ꂩ��A�ǂ������ǂ��ǂ����������A�g�̂͂����䂤�C���[�W���_�͂����䂤�C���[�W�A�Ȃǂ̒P�����͂����A�����̕\�ʓI�Ȃ��̉��ɐ��ޖ{���I�Ȑړ_�������肾�����Ƃɋ��������������Ă��܂��B���̖ʂ����A���������������������ł��B
���Ȃ݂Ɏ��̐e�F�́A�ڂ̏�Q��S���Ă��܂��B�Ȃ�����Ǝ��Ă���ʂ�����A�Жڂ��炵���ڂ��������A�œ_�������܂���B�ނ͂��̃R���v���b�N�X�����z���邽�߂ɂƂĂ��炢�v�������A���ʂƂ��Ă��a���Ă��܂��܂����B�Ȃ̂Ŏ����y���ɂ��u�g�̏�Q�̓R���v���b�N�X�����z����̂����_��Q���ȒP���v�ȂǂƐ錾�����������킯�ł́A�܂���������܂���B
���͔ނ͍ŋ߁A�u���E�A�l�̍��ڂ�ʂ��āiLife Through my Left Eye�j�Ƃ������`�������āA�o�ł��悤�Ƃ��Ă��܂��B�ނ͔ނȂ�ɁA�����̏�Q�ƌ����������@�������āA���͂Ƃ��Ă����������A��������ς�A�܂����ł��i�j�R���v���b�N�X�����z����Ƃ����̂́A��Q�̗ނ͊W�Ȃ��A�X�ɂ���ă^�C�~���O���قȂ�̂�������܂���ˁB
���Ȃ݂Ɂu�ڂ̏�Q�v�Ƃ����̂́u���_�̏�Q�v�Ɠ������A���邢�͎����킵���ʂ�����Ǝ��͊����܂��B�u�ڂɐS���f��v�ƌ����܂����A���̕\���ɂ͐^�ӂ��܂܂�Ă���Ǝv���܂��B
�ł��A��Ԑl�ԓI�Ȃ��̂��A�R���v���b�N�X����I�����ʂ��ĒɊ����Ă����l�X�����A�t�ɂ��̐l�Ԑ�����ԗ��������e�I�Ɏ~�߂�͂���悤�ȋC�����܂��B������A���͂��̕a�C���u�^���I�v���邢�́u���Ԃ��̕t���Ȃ��v�ƐM���Ă��܂����A���̏ꍇ�ɔ����Ċo��͎����Ă��܂����A���������ׂĔے�I�Ɏ~�߂Ă��܂��A�t�Ɏ��̐l�i�ɂƂ��ĕK�R�I�ł���A���̏�ǂ����Ƃ��Ɗ����Ă��܂��B
���X�A���肪�Ƃ��������܂��B�����̍l���������������������ł����悤�ȋC�����܂��i�ǂސl�ɂƂ��ẮA����Ԃ��������ď璷�Ő������Ȃ��Ă��Ȃ��Ɗ������邩�����܂����j
�������A�l�ƃf���P�[�g�ȃg�s�b�N�ɂ��Ă��b���邩����́A����̉��߂⎩���̌��t�̑I�ѕ��ɋC������悤�A�w�߂܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B�ł́B
-�肳
 ����
����  2011/06/29(Wed) 05:11 No.231
2011/06/29(Wed) 05:11 No.231
�@�@���������A���ɂ͂R�O�N�ȏ�̌�F��������g�̏�Q�ҁi�P���j�̐e�F����l���܂��B�i�����j�ނ́A��ڗđR�̔]����აg�̏�Q�҂ŁA���s�E�r�E��E�Ґ����ɏ�Q������܂��B
�ނƂ̌�F���ƁA�����̈ꎞ���̃X�|�[�c��Q�i�A�L���X�F���ؒf�j�̌o������A
����́A�ꌾ�Ō����Ɓw�����x�����邩�������ł��B
���傹��A�a�C�E��Q�̖{���̐h���́A�{�l�łȂ���Ή���Ȃ��Ƃ��v���Ă܂��B
�@�@�o�ΑO�Ȃ̂ŁA�Z�����X���܂����B